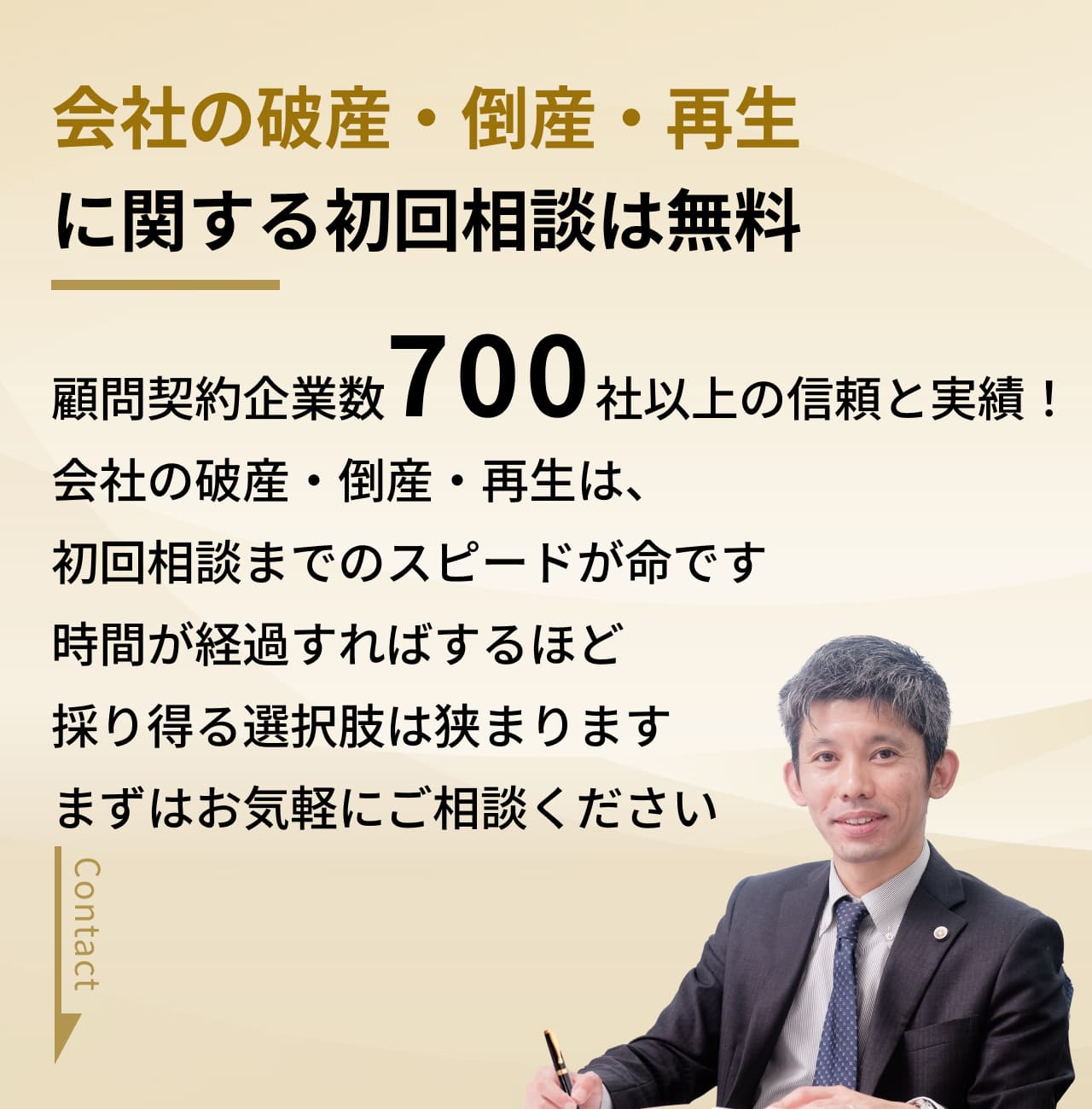昨今、深刻な人手不足や光熱費の高騰、設備の老朽化にともなう修繕費の増大により、宿泊業の経営はかつてない厳しい状況におかれています。「歴史ある旅館を守りたいが、もう限界だ」と、苦渋の決断を迫られている経営者の方もいるのではないでしょうか。
特に宿泊業の場合、以下のような特有の悩みもつきものです。
- 予約客へのキャンセル対応や返金方法がわからない
- 従業員や仕入業者に対してどのような対応をすべきか不安
- 巨大な建物や設備の原状回復、処分に困っている
もし、ホテルや旅館の倒産を検討しているなら、すぐに弁護士へ相談してください。なぜなら、宿泊業は大量の予約キャンセル対応や、複雑なリース契約の整理など、迅速な判断が求められる場面が多く、判断の遅れが地域社会に大きな混乱を招くからです。
適切な手順を踏むことで、混乱を最小限におさえられるでしょう。
本記事では、宿泊業の倒産手続きの流れや注意点について、弁護士が詳しく解説します。最後まで読めば、複雑な問題が整理され、冷静な判断ができるようになるはずです。
この記事でわかること
- 宿泊業が倒産する主な要因
- 予約キャンセルや施設処分などの注意点
- 破産手続きの具体的な流れ
- 弁護士に依頼するメリット
【記事のまとめ】
宿泊業は、人手不足や光熱費の高騰により、非常に厳しい経営状況におかれています。ホテルや旅館の破産手続きでは、予約客へのキャンセル対応や従業員や仕入業者等への周知の時期・方法、大規模な施設の処分など、特有の課題が山積みです。これらを不適切に扱うと、地域社会に大きな混乱を招くリスクがあります。そのため、早期に弁護士の支援を受けることが不可欠といえるでしょう。弁護士に依頼をすれば、複雑な手続きを一任でき、精神的な負担も大幅に軽減されます。適切な整理を進めるために、まずは弁護士法人グレイスへご相談ください。初回相談は無料です。
目次
宿泊業(ホテル・旅館)の倒産・破産における注意点
宿泊業の倒産・破産は、一般企業と比較して、顧客、従業員、地域社会への影響が大きくなる傾向があります。その地域の観光の起点となっていることが多いので、ホテル・旅館の破産は影響が大きいのです。
宿泊業の倒産・破産においては、以下の点について注意が必要です。
宿泊予約者への対応
最も喫緊の課題となるのが、既に宿泊予約をしている顧客への対応です。
予約者には、可能な限り速やかに営業停止の事実と、それに伴う予約のキャンセルまたは代替案(近隣の提携施設への振り替えなど)を伝える必要があります。ウェブサイト、メール、電話など、顧客の予約方法に応じて複数の手法を使い、正確な情報を提供していく必要があります。
既に宿泊代金を受け取っている場合は、速やかに返金手続を進める必要があります。クレジットカード決済の場合は、カード会社との連携が重要になります。不適切な対応は、SNSなどを通じて瞬く間に拡散し、経営者個人や他の関連事業者への風評被害にもつながりかねませんから、誠実かつ迅速な対応が求められます。但し、宿泊代金の返金が破産法上許されない場合もありますから、必ず弁護士にご相談ください。
従業員への対応
次に、従業員への対応が必要です。
宿泊業の破産は、従業員の生活に直結する問題です。営業停止に伴って従業員を解雇せざるを得ない場合、解雇予告期間の確保や解雇予告手当の支払いなど、適切な手続を踏む必要があります。
弁護士の協力も得ながら、解雇理由や今後の見通しについて、十分に説明を行い、従業員の理解を得るよう努めましょう。未払賃金がある場合には、国の立替払い制度を利用するかどうか検討する必要があります。また、従業員の再就職支援として、ハローワークと連携したり、競業他社と連絡を取ったりするなど、可能な範囲での情報提供などを検討すると良いでしょう。
仕入先・業者への未払金と契約解除
また、仕入先・業者への未払金への対応と契約解除の有無についても決める必要があります。
宿泊業者には、食材業者、リネン業者、清掃業者など、多くの仕入先や取引業者があります。未払金がある場合は、破産手続の中で公平に分配されることになりますので、基本的には、個別の業者に対して、独断で特定の業者に優先的に支払うことはできません。
また、同様に、基本的には、各種サービス契約やリース契約などについては、速やかに解除の意思表示を行う必要があります。不必要な費用発生を防ぐためにも、早期の対応が求められます。
地域への影響
最後に、地域への影響に配慮する必要があります。
宿泊施設は、地域経済に与える影響が大きいため、倒産は地域全体に波及する可能性があります。従業員の解雇は、地域における雇用喪失につながります。宿泊施設の閉鎖は、地域の観光客誘致にも影響を与え、関連産業(飲食店、土産物店など)にも打撃を与えます。
地域のイメージダウンにもつながりかねないため、場合によっては、地域住民への説明などが必要とされることもあります。
宿泊業(ホテル・旅館)の倒産・破産手続の流れ
宿泊業の倒産・破産手続は、基本的には、以下のとおり一般的な法人破産手続の流れに沿って進行しますが、宿泊業特有の事情を考慮した対応が求められることもあります。
弁護士へ相談
まずは、経営が悪化したと感じたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。早期に相談することで、事業再生・事業譲渡の可能性を探ったり、破産手続を円滑に進めるための準備期間を確保したりすることができます。
もちろん、そもそも破産するためにもある程度の資金が必要ですから、この意味でも早期の相談が必須です。
また、不適切な対応による法的トラブルを未然に防ぐことができます。宿泊業に詳しい弁護士であれば、業界特有の事情や法規制を踏まえた適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
営業停止・予約対応
弁護士と協議の上、営業停止の時期を具体的に決定し、前述の宿泊予約者への対応を迅速に進めます。この段階で、新たな予約の受付を停止し、既存の予約者への連絡に集中することとなります。
従業員解雇
実際の営業停止と並行して、従業員の解雇手続を進めることになります。必ず弁護士の指導の下、トラブルにならないよう慎重に対応してください。この際には、社会保険の脱退手続や離職票の交付など、解雇時に必要な手続も取る必要があります。
破産申立て
会社の資産・負債状況を踏まえた必要書類を揃え、裁判所に破産手続開始の申立てを行います。申立て後、裁判所は破産手続開始決定を下し、同時に破産管財人を選任します。これ以降、破産管財人が会社の財産を管理・換価する役割を担うことになります。
財産の換価
破産管財人は、宿泊施設の建物、土地、設備、備品などの財産を売却し、現金化していきます(いわゆる換価)。売却代金は、債権者への配当に充てられます。宿泊施設の場合、温泉権や旅館業の許可なども財産に含まれるため、その取扱いは専門的な知識を要します。
宿泊業(ホテル・旅館)の倒産・破産が発生する要因とは?
このような宿泊業の倒産・破産には、複合的な要因が絡み合っていることが多いです。
コロナ後の再建失敗
いわゆる新型コロナウイルス感染症の影響で壊滅的な打撃を受けた宿泊業は、感染症収束後も、資金繰りの悪化、需要回復の遅れ、人材不足と人件費の高騰、投資の失敗といった理由で再建に失敗するケースが見られます。
特に、ゼロゼロ融資で借り入れた金銭を設備投資に充ててしまい、想定以上に利益があがらずにゼロゼロ融資の返済に窮する宿泊業者が増えているようです。
人件費・光熱費の高騰
近年、人手不足を背景とした人件費の高騰や、エネルギー価格の高騰による光熱費の増加が、宿泊施設の経営を圧迫しています。
慢性的な人手不足により、時給の引上げや福利厚生の充実が必要となると、固定費が増加してしまいます。また、電気代やガス代などの高騰は、特に大規模施設にとって大きな負担となります。これらの負担に耐えるだけの体力が無くなってしまう宿泊業者が多いです。
過度な割引・集客依存による収益悪化
また、売上を上げるため、集客のための過度な割引プランを乱発したり、特定のOTA(オンライン旅行代理店)に依存しすぎたりすることで、収益構造が悪化するケースもあります。周囲の施設との価格競争に巻き込まれ、適正な料金設定が困難になることがあります。OTAへの依存度が高いほど、高額な手数料が利益を圧迫します。安価なイメージが定着し、顧客単価の高い層を獲得しにくくなることもあります。
宿泊業(ホテル・旅館)の破産・倒産を弁護士に相談するメリット
宿泊業の倒産・破産において、弁護士に相談することには多くのメリットがあります。
複雑な手続を任せられる
破産手続は、多種多様な法律に基づいた複雑な手続であり、専門的な知識と経験が必要です。法律分野でも、破産は「法律のるつぼ」と呼ばれるくらい複雑な分野とされます。
まさに破産手続について弁護士に依頼することで、裁判所に提出する申立書や添付書類の作成・提出、多数の債権者との交渉や連絡調整、破産管財人との連携や、財産の適正な評価・換価など、複雑な手続全般を任せることができます。
「計画倒産」などの誤解や法的トラブルを避けられる
また、適切な手続きを踏まない場合、「計画倒産」と誤解されたり、債権者からの訴訟など法的トラブルに発展したりするリスクがあります。近年も、倒産した会社の代表者個人が訴訟提起されたり刑事告訴されたりした事案があったことは記憶に新しいです。
弁護士が介入することで、法律に基づいた適正な手続を踏むことができ、不要な誤解やトラブルを回避できます。特に債権者や従業員への説明責任についても、弁護士が適切なアドバイスを行うことで、円滑なコミュニケーションを維持することができる場合があります。
経営者の個人の不安も解消できる
倒産・破産は、経営者にとって精神的にも大きな負担となります。弁護士は、法的整理の道筋を明確に示し、経営者が抱える不安を軽減します。また、破産手続後、経営者個人の生活再建や、新たな事業への挑戦についても、弁護士からアドバイスを受けることができます。
まとめ
以上のとおり、宿泊業の倒産・破産手続についてご説明しました。
宿泊業の倒産・破産は、多方面にわたる影響を及ぼし、その手続も複雑です。早期に弁護士に相談し、適切な対応をとることで、混乱を最小限に抑え、関わる人々の生活や地域への影響を考慮しながら、円滑な手続を進めることが可能です。経営に行き詰まりを感じた際は、一人で抱え込まず、ぜひ、当事務所にご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014