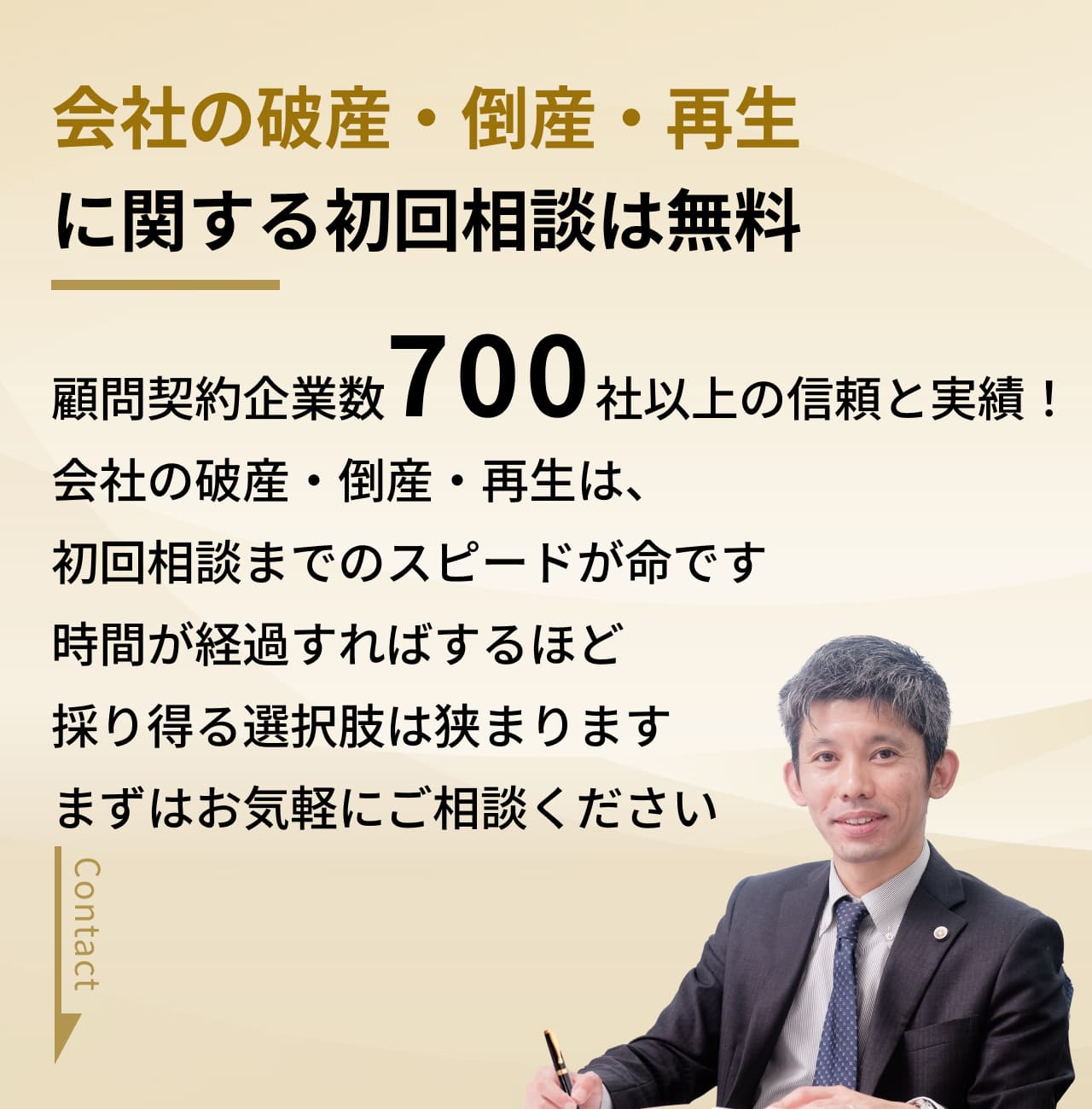民事再生と破産は、どちらも会社の借金(債務)を整理するための法的な倒産手続ですが、その目的と内容には大きな違いがあります。最も大きな違いは、再建をするか否かという点に挙げられるでしょう。
このページでは、民事再生と破産の違いについて解説いたします。
民事再生と破産の違い
まずは、民事再生と破産の違いについてご説明します。両手続は、代表的な倒産手続ですが、以下のように整理することができます。
民事再生:事業や会社の再建を目指す手続。裁判所の監督のもと、債務の一部を減免してもらい、事業を継続しながら返済を進めます。
破産:事業や会社を清算する手続。全ての財産をお金に換え、債権者に公平に分配した上で、会社を消滅させます。
このような違いがあるため、破産は清算型手続、民事再生は再建型手続と言われます。
ちなみに、例えば事業譲渡を利用して優良事業を残しつつ、他の事業を保有した会社を破産させるなど、再建と破産を併用する折衷型の手続選択もあり得ます。
民事再生とは
まず、民事再生は、事業を継続しながら会社の再建を目指す手続です。裁判所の監督のもと、債務の一部をカットしてもらったり、将来の利息を無くして返済期間を延長したりする「再生計画」を立て、債権者の同意を得て実行します。従業員の雇用を守ったり、代々続く企業の強みを残したりすることができる点に利点があります。
経営陣はそのまま事業を続けられるのが一般的ですが、スポンサーに再建費用を支出してもらい、経営層が入れ替わることもあります。
破産とは
他方で破産は、会社の事業を全て停止し、全ての財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。最終的には会社自体が消滅します。
再建の見込みがない場合や、債務が多すぎて事業継続が不可能な場合に選択されます。どちらかといえば、倒産する際には再建の見込みも立たない場合が多いので、破産手続を取る法人の方が多いです。
また、近年はいわゆるベンチャー企業を中心に、新規事業に失敗した場合にはすぐに法人を破産させる傾向があるようです。若い企業ならではの選択といえるかしれません。
破産の要件
ちなみに、破産手続を始めるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
支払不能
会社の資金繰りが悪化し、借金が支払えない状態が続いていること。
債務超過
会社の資産総額よりも、負債総額が上回っていること。純資産額がマイナスになっていること。
このいずれかの条件が満たされている場合に、破産手続開始の申立てが可能となります。代表者個人が法人の債務を連帯保証している場合などには、代表者個人の破産手続も一緒に申し立てることが一般的です。
民事再生で再建可能とされる要素
他方で、民事再生は、上記①②のおそれがある場合に申立てができます。ただし、単に借金の支払が苦しいというだけでなく、将来的に再建が見込める場合に選択すべき手続となります。
再建可能と判断されるための主な要素は以下のとおりです。
安定した収益基盤がある
まず、安定した収益基盤があることです。赤字が一時的で、事業自体には安定した利益を生み出す力があることや、債務負担が軽くなれば、事業が再び黒字に転換できる見込みあることが重要です。
つまり、借金の返済を一時的に免れたり、返済プランを組み直したりすれば黒字化が目指せる程度に収益が上がる事業がなければならないということです。
再生計画の実現可能性が高い
次に、再生計画の実現可能性が高いことも必要です。
債務のカットや返済方法など、具体的に作成された再生計画が現実的で、確実に履行できる内容である必要があります。実際に黒字になる見込みであったとしても、再生計画どおりの借金返済ができなければ、再建できるとはいえません。
経営者に再建の意思と能力がある
また、そもそも経営者が再建に向けて強い意思を持ち、かつ、それを実現するための経営能力があるかどうかも大切な要素です。いわゆる放漫経営によって会社財産を費消してしまうような経営者には、再建を任せることはできません。数値化が難しい観点での要素ですが、経営者が再生手続自体に非協力的ですと、裁判所や債権者から、再建の見込みが無いと評価されてしまいます。
もちろん、会社経営者が民事再生中・再生後の経営に携わる意思を有していることも重要です。支払不能・債務超過のおそれがあるという会社の現状を踏まえて、そこに至った原因を分析・解消するチャンスとなりますから、積極的に再建する意向を示していきましょう。
支援者・支援企業の存在
ちなみに、金融機関やスポンサー企業など、再建を金銭的に、あるいは事業面で支援してくれる存在がいると、再生計画の成功率が高まります。このような民事再生をスポンサー型の手続と呼びます。
倒産手続を多く扱う法律事務所では、スポンサー企業となりうる企業との繋がりもある場合がありますから、弁護士にこの点について確認することも有用かもしれません。
手元資金や運転資金の確保が見込める
また、当然ではありますが、民事再生の手続中も事業を続けることになるため、一定の手元資金が残っているか、又は当面の運転資金が確保できる見込みがあることが不可欠です。手元資金もなく、運転資金を確保する見込みもなければ、そもそも民事再生手続中に資金ショートして破産することとなってしまいます。
もちろん、民事再生手続自体にも、一定の費用がかかります。
会社の流動資産の余力を失ってしまう前に、早期の段階で弁護士にご相談・ご依頼をいただけますよう、ご注意ください。
適切な選択をするには
それでは、あなたの企業にとって適切なのは、どちらの手続でしょう。民事再生か破産か、どちらが適切かは、会社の状況によって異なりますから、必ず専門家の意見を確認するべきです。基本的な視点は、以下の点から整理することができます。
目的や現状を整理する
まずは、会社の資産・負債、キャッシュフロー、事業の収益性などを正確に把握し、再建の可能性があるのか、それとも清算するべきなのかを冷静に判断しましょう。特に経営者自身の人生設計によっても、目的は左右されますから、注意しましょう。
現状を客観的に整理した上で、数値を基本に据えて検討をすることが重要です。この際には、実際に民事再生を選択した場合にどの程度の支払まで抑えることができるのかなど、民事再生手続を取り扱う弁護士にご相談いただくことが重要です。
債権者等の協力を得られそうか
また、民事再生には、少なくとも債権者の過半数の同意(厳密には、①債権者数の過半数の同意かつ②債権総額の2分の1以上の債権を有する者の同意)が必要です。債権者と日頃から良好な関係を築けているか、あるいは債権者が再建に協力してくれる可能性が高いかどうかも重要な判断材料です。特定の債権者は民事再生に非協力的であるなどの情報もありますから、事前に協力を得られるかの目途を立てることもできます。
加えて、民事再生時に提案する再生計画がどれだけ現実的かつ具体的なものになるかどうかも、債権者の同意を得る上で重要となります。
民事再生、破産に強い弁護士へ相談
いずれの手続を取るにせよ、民事再生も破産も複雑な法的手続であり、隣接する法分野も含めて専門的な知識が不可欠です。これらの分野に詳しい弁護士に相談することで、客観的な視点から最適な選択肢についてアドバイスを得ることができます。
また、これらの分野に詳しい弁護士に依頼することができなければ、民事再生手続が途中で頓挫する自体にもなりかねません。依頼する弁護士自体も慎重に精査した上で手続をとることが肝要です。
まとめ
以上のとおり、民事再生と破産の違いについて弁護士の視点からご説明しました。民事再生をご検討されているとすれば、どのような手続と取るべきか、決断に大きな勇気が必要となります。経営者として、会社の未来を左右する重大な選択に直面されている今、様々な不安や迷いがあることでしょう。そのような中で、民事再生は、会社の再起に向けたリスタートの手続として機能します。ぜひ、破産手続だけでなく、民事再生手続も視野に入れてご検討ください。
民事再生をご検討の場合には、ぜひ、当事務所までご相談ください。当事務所には、多くの倒産事件を取り扱ってきた確かな実績があります。会社の借金問題・債務超過問題にお悩みの場合には、実際に倒産手続を取らないというご判断をなされても問題ありませんので、一度お問い合わせいただければと存じます。お悩みのあなたからのご相談を、お待ちしております。
 0120-77-9014
0120-77-9014