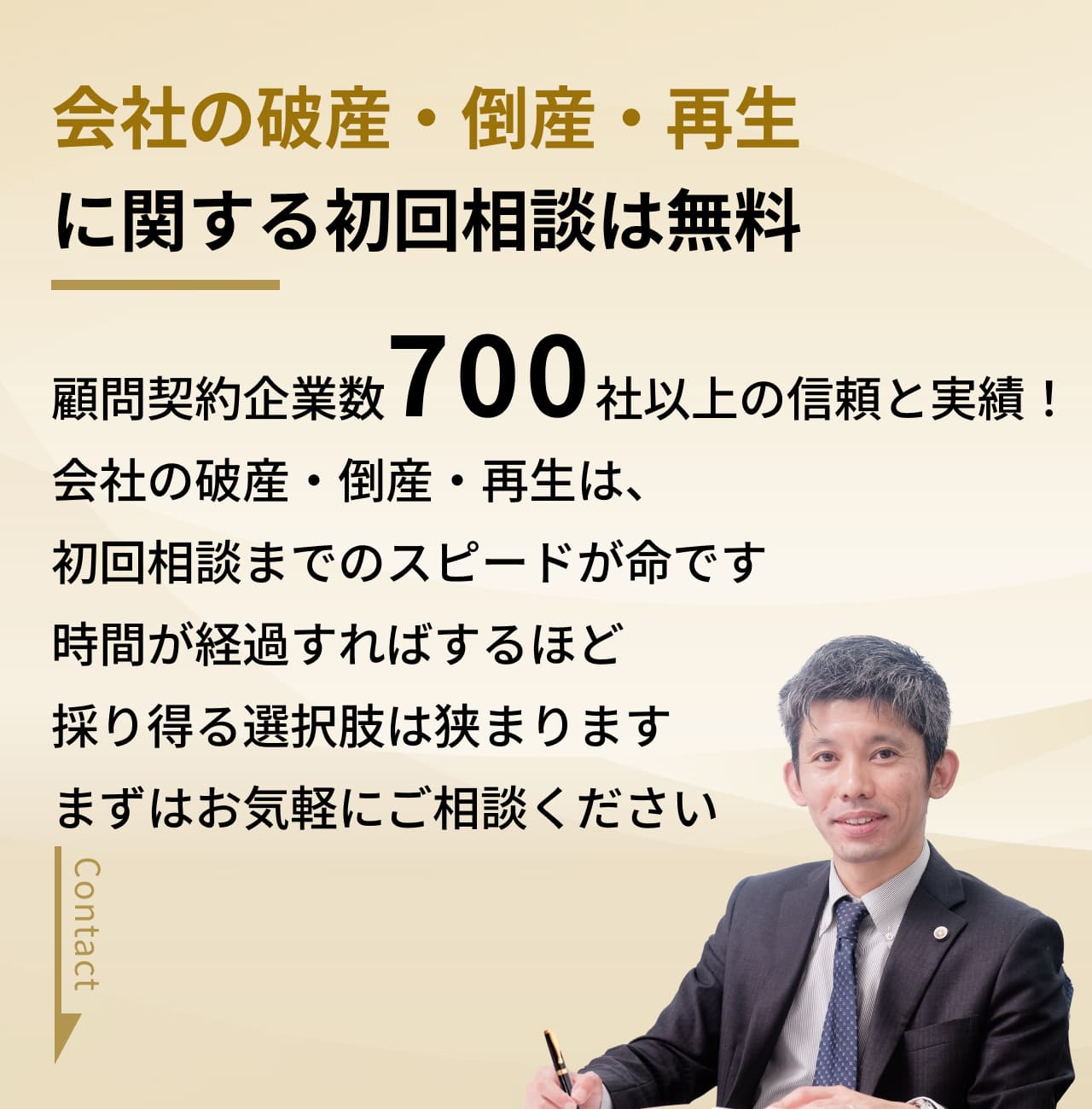経営危機に直面した企業が再建を目指して債務を整理する方法の一つに、「私的整理」があります。これは、破産・民事再生などのように裁判所を用いるのではなく、債務者である企業と債権者(主に金融機関)との自主的な協議によって、債務の減免や返済スケジュールの変更(リスケジュール)などを図る手続です。借金を満額返せない又は今の利息を支払ってはいけない、といった会社のうち、事業再生の見込みがある場合には、私的整理も検討することとなります。
企業の債務整理には、この私的整理と、裁判所主導で法律に基づいて進める「法的整理」(民事再生や破産など)の2種類があります。ここでは、私的整理について解説していきます。
私的整理とは?
私的整理は、法的な枠組みにとらわれず、当事者間の合意に基づいて進められる債務整理手続全般を指します。純粋な任意交渉によるものから、第三者機関が策定したガイドラインや支援スキーム(事業再生ADR、中小企業再生支援協議会による再生支援など)を利用する「準則型私的整理」まで、様々な方法があります。
一般に、対象となる債権者は金融機関などの主要債権者に限定し、仕入先などの一般的な債権者は対象としないケースが多いです。これにより、事業の継続に必要な取引関係を維持しながら再建を図ることが可能になるのです。
私的整理のメリット
私的整理には、以下のとおり、法的整理にはない大きなメリットがあります。
外部に知られにくい
私的整理であれば、交渉を行う債権者以外の外部者に、債務整理を行っていることが知られにくいです。
法的整理は、裁判所への申立てが公告されるため、報道等によって企業の信用が大きく低下し、取引先や顧客離れを招くリスクがあります。もちろん、法的整理を利用した場合、その後になにがしかの融資を受けることは極めて難しくなるでしょう。一方、私的整理は非公開で進められるため、外部への情報漏洩を防ぎ、事業価値の低下を最小限に抑えることができます。
会社を続けながら借金を整理できる
私的整理であれば、会社を続けながら借金を整理することができます。
私的整理の主な目的は、事業の再生です。このため、私的整理においては、債務を整理しつつ本業を継続することで、企業の再建を目指します。破産であれば法人自体が無くなってしまいますから経営はそこで終了してしまいますが、私的整理を利用する際には、経営者自身が再建後の経営を継続できる可能性も、法的整理に比べて高くなります。
経営者が、どのような事業再生計画を練ることができるかが肝であるともいえるでしょう。
手続が柔軟でスピード感がある
また、私的整理であれば、手続が柔軟でスピード感があります。
裁判所の関与がないため、法律上の厳格な制約がなく、企業の状況や債権者の意向に応じて、様々な事情を考慮した上で、柔軟な再生計画を立てられます。また、裁判所の手続を待つ必要がないため、合意さえ得られれば迅速に手続を終えることが可能です。早期の解決を図って事業再生のための活動に繋げる場合には、私的整理が最適といえます。
私的整理のデメリット・限界
一方で、私的整理には以下のような限界があるため、すべてのケースで選択できるわけではありません。
債権者全員の合意が必要でハードルが高い
まず、私的整理においては、交渉対象となる債権者全員の合意が必要となるため、ハードルが高いです。
私的整理は、裁判所による強制力がないため、債務の減免や返済条件の変更について、対象となるすべての債権者の合意が必要です。一人でも反対する債権者がいると、原則としてその計画が成立せず、計画の練り直しが必要となります。
1社でも反対すれば成立しない
裏を返すと、1社でも私的整理案に反対する債権者がいれば、私的整理の計画が成立しないといえます。ここが大きな限界といえます。
特に、銀行などの金融機関が複数いる場合、それぞれの立場の違いから利害調整が難航し、「たった1社」の反対で計画が頓挫してしまうリスクがあります。
実務上は銀行との調整が非常に難しい
また、私的整理においては、実務上、銀行との調整が非常に難しくなります、
金融機関は、自己の貸付債権の回収最大化を目指すため、債務免除などの負担を負うことに慎重です。特に、企業が提出する事業計画の実現性や、経営陣の責任の明確化について厳しく審査されるため、専門家(弁護士や公認会計士など)の関与のもと、説得力のある交渉を進めることが必要不可欠です。
破産・民事再生の違い
私的整理が難しい場合、裁判所を利用する法的整理を検討します。法的整理には、主に「清算型」の破産と「再建型」の民事再生があります。
破産
まず、破産についてご紹介します。
破産手続は、会社を清算し、残った財産を債権者に公平に分配して、法人格を消滅させる手続です。事業継続の可能性が完全に失われた場合や、私的整理・民事再生の見込みがない場合に選択されます。会社が無くなる以上、経営者は会社から退くこととなりますから、その後の転職等が必須となります。
民事再生
次に、民事再生についてご紹介します。
民事再生手続は、裁判所の監督のもと、事業を継続しながら債務を大幅にカットし、会社の再建を目指す手続です。民事再生は、法的整理でありながら再建型であるため、私的整理のメリット(会社継続)と法的整理のメリット(強制力)を併せ持ちます。しかしながら、手続は公開され、信用への影響は避けられません。会社が存続するため、原則として、経営陣は会社に留任することができます。
私的整理が難しいケースとは?
ちなみに、以下のようなケースでは、私的整理での合意形成が困難となり、法的整理を選択せざるを得なくなります。
- 対象となる債権者が多数にわたり、利害関係の調整が極めて難しい場合。
- 連続する不払など、主力債権者(メインバンクなど)との信頼関係が既に崩れており、協力を得られない場合。
- 事業計画が非現実的で、債権者が債務免除等の負担を受け入れるだけの説得力に欠ける場合。
- 負債額が過大で、事業再生によっても返済可能なレベルまで債務を圧縮できない場合。
- 手形や売掛金などの一般債権も整理対象に含めないと再生できないなど、交渉相手の性質上、私的整理では対応できない場合。
早めに弁護士に相談するのが最善策
さて、以上のとおり、私的整理について解説するとともに、経営者が知っておくべき選択肢とその限界についてご説明しました。
私的整理は、法的整理に比べて非公開性や柔軟性という大きなメリットがありますが、そのハードルは非常に高いのが実情です。会社の現状を正確に分析し、どの手続(私的整理、民事再生、破産)が最善かを判断するためには、事業再生の経験が豊富な弁護士のサポートが不可欠です。早めに弁護士に相談することで、事業価値の低下を食い止め、選択肢の幅を広げることができます。
危機を乗り越え、企業を再建するための第一歩は、専門家への相談であることをご理解ください。当事務所では、法人破産手続を多く扱ってきた実績があります。借金についてお悩みの場合には、破産・民事再生などの他の手続との比較をしながら、あなたの会社にフィットする方法をご助言できます。ぜひ、お困りの際には当事務所までご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014