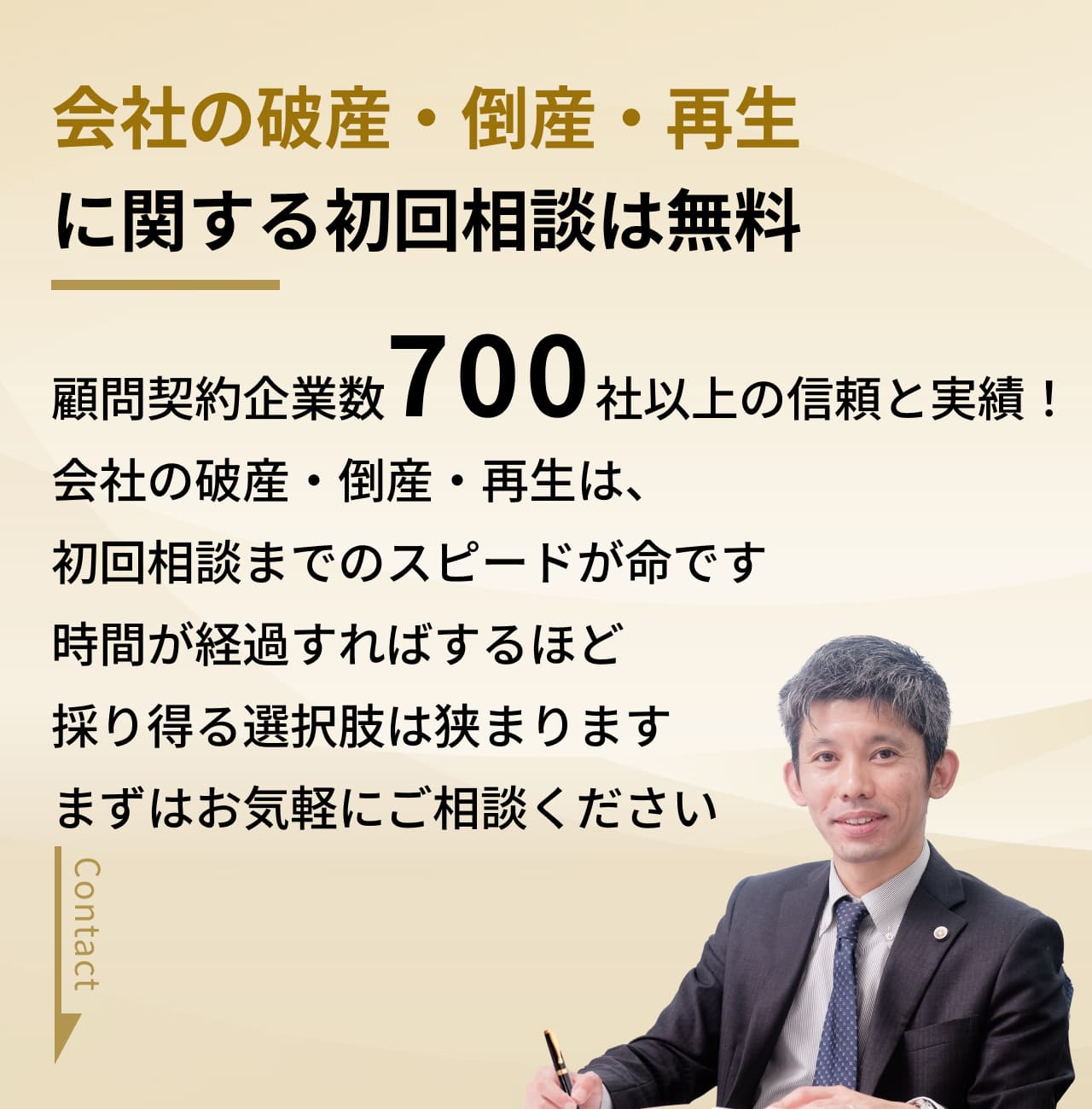建設業の元請け業者が倒産する場合、下請け業者にはどのように対応すれば良いのか、悩まれる方が多いでしょう。工事の報酬金は支払うべきか、未着手の工事がある場合にはどうすれば良いか、など、多くの法的問題が介在します。
このページでは、この点について、弁護士の視点から解説していきます。
目次
建設業の元請け業者が倒産する場合の下請け業者への対応
建設業の元請け業者が倒産する場合の下請け業者への対応について、まずはご説明します。
状況説明と情報共有
まず、元請業者として経営状況の異変(支払遅延、不渡り、弁護士からの受任通知等)を把握した時点で、弁護士に相談のうえ、下請業者に対し、事実関係と法的見通しを速やかに説明すべきか否か判断する必要があります。元請業者が取る予定の倒産手続と今後の流れについて、下請け業者に誠実に共有することで、下請け業者に深刻なダメージが及ぶことを防ぐことができます。
ただし、倒産手続の種類・方法によっては、下請け業者への通知を避けるべき場合もありますから、この点については必ず弁護士ご相談ください。
工事の進行状況確認
次に、工事の進行状況を確認して整理しましょう。
下請け業者としては、倒産手続開始の通知を受けた場合、工事の続行は原則として停止させるでしょう。続行すると、新たな債権(未払い代金)が発生し、回収不能のリスクが高まるためです。この点は理解しておく必要があります。そこで、資材の搬出防止・仮設物の撤去・安全管理の徹底など、現場の混乱を最小限に抑えるための指示を行う必要性がでてきます。
発注者への連絡
このように、下請け業者と情報を共有して工事の進行状況確認・工事現場の保全をした後で、発注者に対し、倒産手続をとることと契約解除の通知を出していくこととなります。この際には、下請業者から発注者への連絡について、工事の進捗や未払額など、必要な正確な情報を提供し、下請業者と発注者間で今後の工事継続に関する協議がスムーズに行えるよう調整しておきましょう。こうすることで、発注者等の関係者への影響を抑えることができます。
債権届出の案内
特に、選択する倒産手続が破産の場合、工事代金のうち、届出がなされた未払分については配当の可能性が生じます。このため、下請業者に対し、債権届出の期限、方法、必要書類を案内することとなります。通常は、代理人弁護士が倒産手続を取ることを通知するのと同時に、これらの手続の案内をすることとなります。
弁護士から下請け業者に対する法的手続
下請け業者の中には、倒産手続をとると聞いた場合に、下請業者からの個別の問い合わせや、留置権の主張、債権者代位権の行使など、下請業者が取り得る法的手段に関する通知をしてくる場合があります。これらの連絡窓口となり、元請け業者の対応を整理・調整するのが、弁護士の役割となります。
場合によっては、弁護士から下請け業者に対して法的手続を取る場合もあります。
建設業の元請け業者が倒産するときの注意点
建設業の元請業者側が倒産するときには、以下の点への注意を要します。
下請業者・発注者との調整
まず、下請け業者や発注者との調整に注意が必要です。
下請業者や発注者に対しては、法的に許される範囲で誠実に対応し、情報公開の透明性を保つことが有益です。これは、後の手続がどの程度円滑に進むかに大きく影響します。
この際には、未完成工事について、発注者と次の施工業者の選定・引継ぎに関する協議を迅速に行い、元請業者としての協力義務を果たすことが重要です。
未収金・工事代金の回収
次に、未収金・工事代金の回収にも注意を要します。
元請業者が発注者に対して有する工事代金債権を回収する場合には、回収金を勝手に利用することなく、保管・保全しておくことが必要となります。この回収金は、倒産手続において、下請業者を含む債権者への配当原資となります。
ただし、倒産手続開始直前に、特定の下請業者だけに工事代金を支払う(偏波弁済(へんぱべんさい))ことは厳禁です。これは否認権の対象となり、管財人によって取り消され、のちに下請け業者が金銭を返還するよう請求されることになります。かえって下請け業者に迷惑を掛けてしまいますので、注意しましょう。
現場の混乱を最小限に抑える
工事現場の混乱を最小限に抑えることも重要です。資材の流出、盗難などを防ぐため、現場の閉鎖、警備の手配などの緊急措置を講じましょう。特に最近は、建材や工具、金属類の窃盗が増加していますから、早急な対応が必要となります。
建設業法による保護制度
元請け業者が倒産する場合(または倒産寸前の場合)、下請け業者には、以下のように建設業法による保護がなされています。元請け業者としては、下請け業者へ迷惑を掛けることを必要以上に恐れないようにしましょう。
直接請求制度
建設業法上、特定建設業者が元請負人として受注した工事については、下請負人に対して未払となっている報酬金について、立替払い等の適切な措置をとるよう、監督官庁が特定建設業者に対し、勧告することができます(建設業法41条)。
ちなみに、下請け業者としては、債権者代位権(民法423条)を行使して元請業者の発注者に対する請求権を代位行使することや、工事目的物に対する留置権(民法295条)の行使を検討することもできます。
公共工事と民間工事の違い
公共工事の場合には、公共工事標準請負契約約款に、元請業者の倒産等による解除の場合、発注者が下請業者等に出来高に応じた相当の金額を直接支払うことができる旨の規定(履行保証契約に伴う規定等)が設けられていることがあります。
他方で民間工事では、当事者間で締結した契約約款・契約書に同様の規定がなければ、上記の債権者代位権や留置権の検討が主となります。
保証会社・履行保証
上記のとおり、公共工事や、大規模な民間工事では、履行保証契約が付されていることがあります。これは、元請業者が倒産などで工事を完成できなかった場合、保証会社が代わりに工事を完成させたり、発注者や下請業者の損失を補償したりする制度です。下請業者の未払代金の回収につながる可能性があり、この点でも下請け業者が保護される余地があります。
建設業の元請け業者が倒産するときに弁護士に相談するメリット
元請業者が倒産を決断した際、弁護士に相談することで以下のメリットを得られますから、手続の適正化と関係者への対応の質を高めることができます。
未払代金の回収サポート
まず、弁護士は、発注者からの未払金の回収をサポートしてくれます。
弁護士が発注者に対し、元請業者の工事代金債権について仮差押え等の債権保全措置を迅速に講じることもできますから、発注者が元請業者以外に誤って代金を支払うことを防ぐとともに、配当原資の確保も図れます。
下請けへの対応がより誠実なものになる
また、弁護士が窓口となることで、下請業者に対し、建設業法、民法、倒産法等の法的根拠に基づいた説明と、公平・中立的な対応が可能となり、元請業者側の誠実性を示すことができます。弁護士による回答であれば、下請け業者も納得感を得やすいでしょう。
他の債権者との調整がスムーズに
更に、多数の債権者(下請業者、資材業者、金融機関等)からの問い合わせや請求に対し、弁護士が一元的な窓口となり、各種法令に基づく統一的かつ公平な処理を進めることで、手続の混乱を避け、スムーズな進行を可能にします。
法律の専門家たる弁護士に相談・依頼することならではのメリットといえるでしょう。
まとめ
以上のとおり、建設業の元請け業者が倒産する場合の下請け業者への対応と注意点について解説しました、元請け業者としては、下請け業者に気を遣い過ぎることなく、弁護士の助力を得ながら倒産手続を進めることが重要といえます。下請け業者に気を払って倒産処理が遅れると、かえって多くの関係者に迷惑を掛けることとなります。
当事務所では、建設業を営む法人の倒産処理を多く扱ってきた実績があります。倒産手続をお考えの場合には、ぜひ、当事務所までご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014