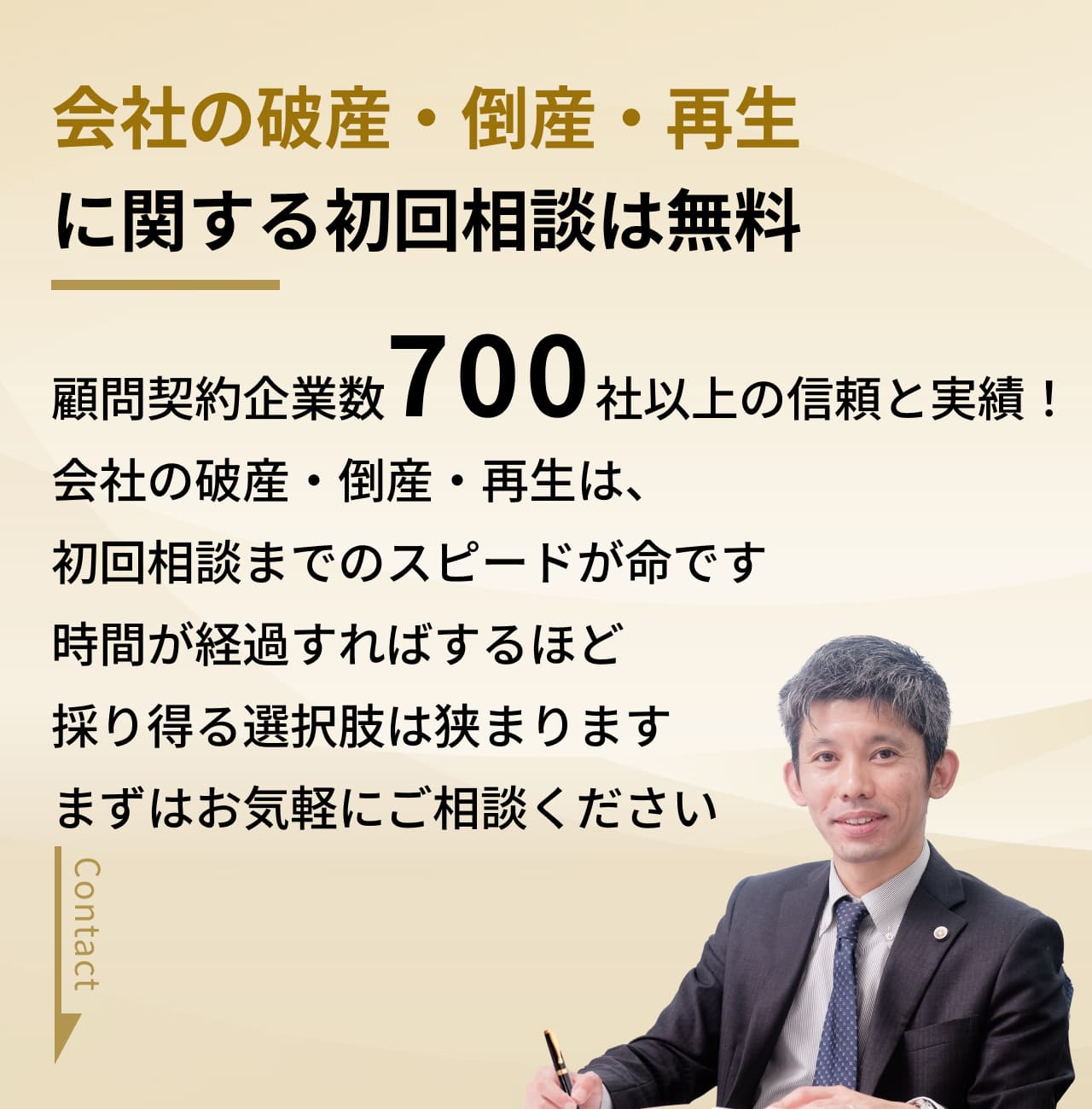建設業の下請け業者が倒産する場合、元請け業者にどのような対応を取っておくべきか、悩ましいところでしょう。このページでは、倒産する場合に元請け業者に対して必要となる対応と注意点について解説します。
目次
建設業の下請けで最も避けたい「突然の倒産」元請けへの報告を怠るリスク
建設業における下請け業者の「突然の倒産」は、元請け業者にとって現場の停止や代替業者の手配など、甚大な損害をもたらす事態です。倒産を決意した下請け業者が、元請けへの報告を怠り、秘密裏に手続を進めようとすることは重大な結果を招きかねません。
特に、倒産することを予定しながら新たな工事を受注するなどの行為は、厳に慎むべきです。倒産手続中に、元請け業者や発注者から「詐欺である。」などと指摘されたり、場合によっては代表者が逮捕されたりする事案もありますから、注意しましょう。
また、倒産することを隠して手続を進めると、「誠実性に欠ける。」と判断され、その後の元請けとの交渉や、破産手続における協力関係構築が難しくなります。適切なタイミングで、倒産見込みであることを誠実に伝えることが、後の問題を最小限に抑えるための鉄則です。
【タイミングが重要】元請け業者へ倒産の事実を伝える最適な方法
それでは、元請け業者へ倒産の事実を伝える場合に重要な点について解説します。
ベストなタイミングは「弁護士に依頼した後」
倒産の事実を元請け業者に伝える最適なタイミングは、正式に破産手続の準備を弁護士に依頼した後です。
弁護士に依頼する前は、経営者自身も今後の見通しや法的な影響を把握しきれていないため、曖昧な情報しか伝えられません。このような時点では、かえって元請けの不安や不信感を増幅させるだけです。弁護士が介入することで、全ての窓口が弁護士に一本化されますから、この時点で元請け業者に倒産することを伝え、弁護士を通してやり取りするようにしましょう。
誰が伝えるべきか?|経営者本人と弁護士の役割
倒産の事実は可能な限り弁護士を通じて元請けに伝えるべきです。なぜなら、倒産の事実を初めて聞かされる立場からすれば、種々の質問をしたり、今後の対応策を求めるのが通常でしょう。しかしながら、倒産手続は専門的知識を要する法的手続ですので、経営者本人が対応することは新たなトラブルを招きかねません。そのため、どうしても経営者本人がこれまでの取引に対する謝罪や誠実に対応する意思を伝えたいのであれば、弁護士からの通知の後に、弁護士からの助言を得て行うべきです。
弁護士は受任通知という書面を送ることで、正式に倒産予定であることを通知し、今後の手続の見通し、特に元請け業者との工事契約の解除の有無や債権債務の整理について協議することとなります。弁護士は、専門家として窓口となり交渉します。元請け業者からの損害賠償請求や資材の引渡要求などは、のちに問題にならないように、全て弁護士が対応するべきです。
伝えるべき内容と注意点|感情的にならず誠実な対応を
仮に元請け業者に対し弁護士を通さずに連絡しなければならない事態となった場合には、元請け業者に伝えるべき核となる内容は、以下のとおりです。
- まず、倒産手続をとることとなったことを伝えます。
- 次に、工事の続行が不可能となったことを伝えます。元請け業者からは叱責があると想定されますが、誠実に対応しましょう。
- 最後に、弁護士に全ての対応を任せたことと、担当弁護士の連絡先を伝えます。
注意点は、感情的にならず、誠実な姿勢で臨むことです。「あなたには必ず支払う」など、実現不可能な約束や見通しのない回答は絶対にしてはいけません。また、特定の元請け業者にだけ優遇的な対応をすることも、債権者平等の原則に反するため避けるべきです。一部の方にだけ返済をすると、かえって、のちに裁判所が介入した際に問題視されて相手に迷惑を掛けることとなります。
元請け業者から想定される対応と下請けとして準備すべきこと
次に、元請け業者からの想定される対応と、下請け業者として準備すべきことをご説明します。
工事請負契約に基づく損害賠償請求や違約金の発生
倒産による工事の履行不能は、通常、工事請負契約上の債務不履行にあたります。元請け業者からは、代替業者の手配費用や工期遅延による損害など、損害賠償を請求してくることが想定されます。
下請けとして準備すべきは、契約書や注文書を整理し、請け負っている工事の進捗状況、現場に投入済みの費用などを正確に記録しておくことです。元請け業者からの請求は、破産手続の中で破産債権として扱われることになります。
また、訴訟は、破産手続中は、破産管財人という裁判所が選任した弁護士が担当することとなります。
現場にある資材や重機・工具はどうなる?
それでは、現場にある資材や重機・工具はどうなるのでしょうか?現場の資材等の所有者によって、対応が異なる点に注意が必要です。
基本的に、下請け業者所有の資材・重機・工具は、破産手続の中で現金化)されて配当に回されます。他方で、元請け業者所有の資材(貸与材など)や、リース物品については、所有者への返還をすることとなります。
このため、下請けとしては、現場の資材等について、その所有者がわかる資料(領収書、リース契約書など)を整理し、元請けと弁護士に共有できるように準備することが必要といえます。
売掛金は回収できるのか?相殺のリスクについて
倒産を選択するのであれば、売掛金の回収も、基本的には弁護士に委ねることになるでしょう。元請けに対して有する未払いの工事代金(売掛金)債権は、配当金を構成する重要な資産ですので、可能な限り回収するべきです。
しかし、元請け業者は、前述の損害賠償請求権や、下請けに預けていた前渡金などを根拠に、売掛金との相殺を主張してくる可能性があります。元請け業者からの相殺が認められるかどうかは法律上に定められた基準に則って判断することとなりますので、下請けとしては、元請け業者からの相殺提案に安易に応じることは避けましょう。
必ず、弁護士の判断に委ねるべきです。
保証人・連帯保証人への請求の可能性
金融機関や取引先からの借入に対して、経営者個人が保証人・連帯保証人になっている場合、会社の破産手続中に、保証人個人に対する請求があるでしょう。このため、会社の破産とは別に、経営者個人の破産も視野に入れる必要があります。
下請け業者としては、まず契約書を確認し、保証債務の総額を把握して破産という選択を取るべきか検討をする必要があります。
破産手続き開始後の「破産管財人」との交渉
破産手続が開始されると、裁判所によって選任された破産管財人が会社の財産の管理処分権を持つようになります。破産管財人が、破産する会社の財産の換価・配当を行うのです。
このため、破産手続においては、元請け業者との交渉を含む全ての法的行為は、破産管財人が窓口となって進めます。下請け会社の経営者は、管財人に誠実に協力し、必要な情報を提供することに徹しましょう。
建設業の倒産を弁護士に相談すべき理由
さて、以下では、建設業の倒産を弁護士に相談するべき理由についても解説します。
理由1:元請けや債権者との交渉窓口となり、精神的負担を大幅に軽減できる
弁護士に依頼した時から、元請け業者やその他の債権者からの直接的な督促や交渉の窓口は、全て弁護士が担います。これにより、経営者は精神的な重圧から解放され、手続に必要な資料の準備や、経営者個人の将来設計などに集中できます。
理由2:あなたの状況で最適な法的手段(破産、再生等)を判断してくれる
また、弁護士は、会社の財務状況、債務超過の程度、事業継続の可能性などを総合的に判断し、そもそも、破産(清算)、民事再生(再建)などのうちからどのような手段をとるべきかアドバイスできます。最適な法的手段を提案できるのは、弁護士ならではのメリットでしょう。
理由3:守れる資産を最大化し、経営者の再起をサポートしてくれる
更に弁護士は、経営者の自由財産(破産後も手元に残せる財産)を最大限に守りつつ、経営者個人の破産(同時破産)も含めた再起のためのプランをサポートします。会社が無くなっても経営者個人の人生は続きますので、そこまで含めて弁護士の助力を受けることをお勧めします。
よくあるご質問
また、下請け業者から破産のご相談を受ける際によくあるご質問に対し、以下のとおり、回答いたします。
Q. 進行中の現場はどうすればいいですか?元請けから損害賠償を請求されますか?
A. 進行中の現場は、弁護士と協議の上、直ちに工事を中止しましょう。元請け業者は、債務不履行に基づき、代替工事費や工期遅延による損害賠償を請求してくる可能性が高いですが、これは破産債権として扱われ、破産手続の中で法的に適切に処理されます。
Q. 元請けから支払を受けていない工事代金(売掛金)があります。これは回収できますか?
A. 売掛金は配当対象財産となります。元請け業者から相殺の主張が出される可能性や工事の瑕疵などの主張を受けることが多く、全額回収は困難な場合が多いです。相殺の可否などの法的判断は弁護士が行いますので、経営者が勝手に回収したり、相殺に応じたりすることは避けてください。
Q. 現場に置いている自社の工具やリース会社の重機はどうなりますか?
A. 自社の工具は破産財団に含まれます。他方で、リース会社の重機の所有権はリース会社にありますから、弁護士を通じてリース会社に連絡し、引き取りの手配をすることとなります。元請け業者に工具等の返還を求める場合も、弁護士または破産管財人が窓口となりますので、ご自身で勝手に対応しないように注意しましょう。
Q. 滞納してしまっている社会保険料や税金も、破産によって支払いが免除されるのでしょうか?
A. 会社が滞納している社会保険料や税金は、破産手続によって法人が無くなるので、消滅します。しかし、経営者個人に課される社会保険料や税金は、破産手続の中で免除されない(非免責債権)ので、注意が必要です。
まとめ
以上のとおり、建設業の下請け業者が倒産する場合の元請け業者への対応と注意点について解説しました。
下請け業者の倒産は、元請け業者との関係清算という複雑な問題を含みます。最善の対応は、早期に弁護士に相談し、元請け業者に対して誠実かつ法的な対応窓口(弁護士)を明示することです。感情的な対応を避け、法的な手続きに則って全ての債務・債権を整理することが、経営者の再起への第一歩となります。当事務所では、多くの法人の倒産案件に対応してきました。お悩みの際には、ぜひ、ご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014