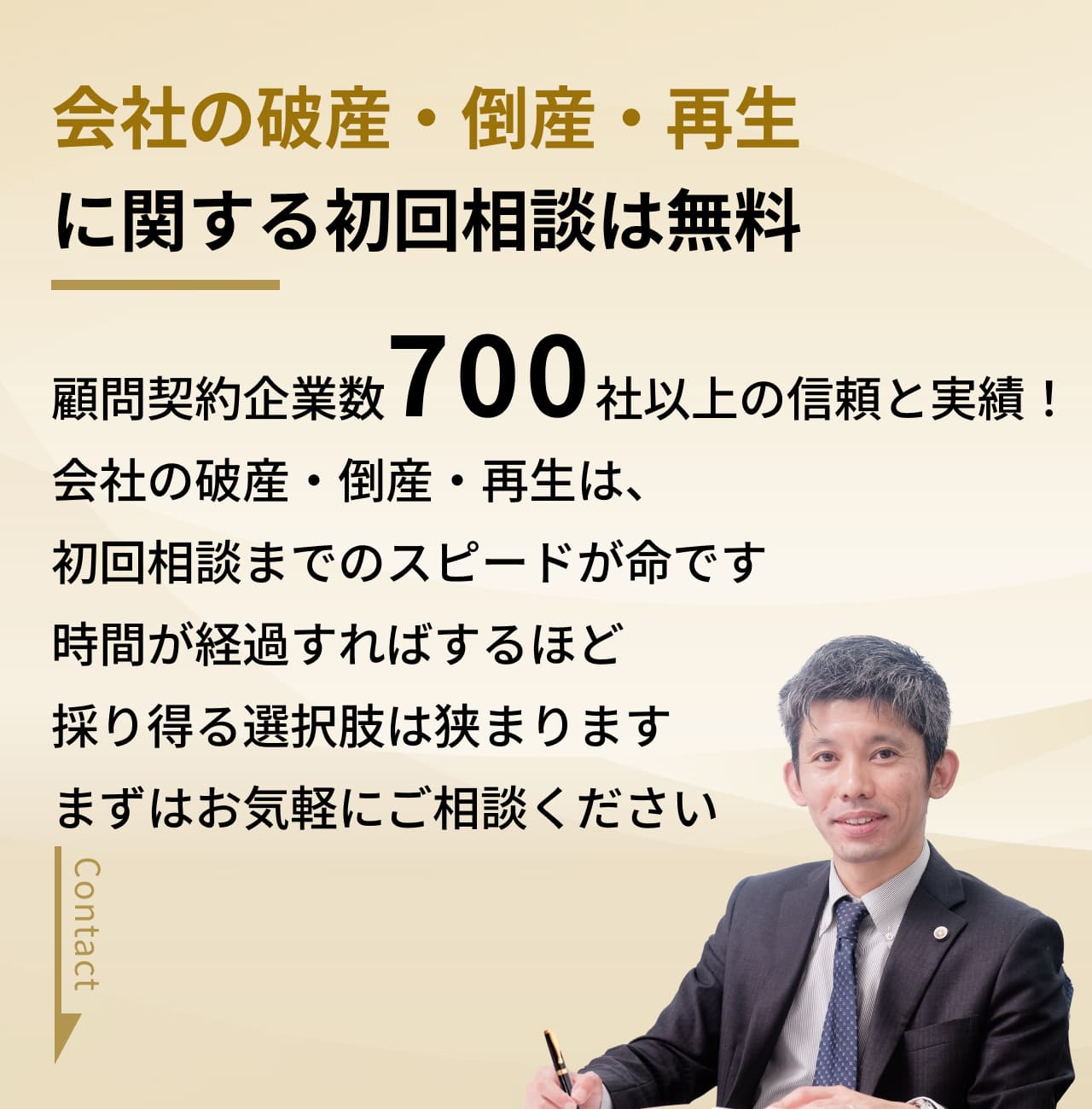2024年は、建設業者・建設業界での倒産・破産事件の増加が目立っています。帝国データバンクの発表によれば、建設業・建設企業の倒産件数は1890件で、過去10年間で最多のようです。
物価高騰の影響から各種原材料が高騰し、建設業者の利益が上がりにくくなっていることが大きな一因でしょう。建設業者が倒産すると、下請業者への工事代金の支払がなされなくなり、連鎖的に下請業者・個々の職人の破産という事態も起きてきます。
以下では、建設業の倒産・破産手続の流れと注意点を解説いたします。
目次
建設業・建築業の倒産・破産が発生する要因
そもそも、建設業・建築業の倒産・破産が発生する要因はどこにあるのでしょうか。主な要因としては、以下の4種類が挙げられます。
資材価格の高騰と経済状況の変動
まず、物価高により資材価格が高騰しているなど、経済状況の変動があります。昨今は急激な物価高や原材料価格の高騰がどんどん起きています。これによって資金繰りが圧迫されることとなります。
また、資材価格の高騰は、原価を削る行為につながりますから、企業によっては人件費を削ろうと躍起になっている会社もあるようです。これでは、労働者が離れてしまって、更に利益率が下がっていってしまいます。
こういった悪循環が、建設業界全体を渦巻いているのです。
人手不足と労働環境の課題
次に、人手不足と労働環境の課題も挙げられます。建設業者・建築業者においては、長時間労働の問題や、労働環境が悪くなりがちな点から、従業員・業界全体の高齢化の問題が叫ばれています。
これでは労働効率も下がり、生産性も落ちていってしまいますから、建設業者・建築業者の破産件数が増えていても何らおかしくはないでしょう。
受注の減少と競争の激化
更に、受注の減少と競争の激化も昨今の問題です。建設業者間でも競争が激化してしまい、受注件数が減少していき、結果として利益を上げられなくなる企業が増えてきているのです。
資金繰りの悪化と債務超過
上述したような各問題から、資金繰りが悪化して、徐々に債務超過に追いやられていってしまいます。新型コロナウイルス感染症蔓延時の、いわゆるゼロゼロ融資の返済期限が到来したことも、各社の資金繰り悪化の一要因となっています。
建設業界全体が、厳しい岐路に立たされているということができます。
建設業・建築業の倒産・破産における注意点
それでは、建設業・建築業の倒産・破産時には、どのようなことに注意すれば良いでしょう。主に、以下のような点に注意が必要です。
労働者・職員への対応と労務管理
まずは、労働者・職員への対応と労務管理が必要となります。長時間労働が常態化してしまっていた場合には、残業代計算も未了で債権額が分からないこともあります。これらの労務管理確認と、解雇手続を取っていくことに注意が必要です。
元請け・下請け等関連業者への影響
元請業者・下請業者等の関連業者への影響も考慮して方針決定をする必要もあります。特に建築業者は、上述のとおり、下請業者になるほど中小零細企業となるので、元請業者の破産をきっかけに連鎖的な倒産が発生することがあります。この点にも留意しながら倒産手続を進める必要があります。
建築請負契約について
更に、建築請負契約についても、特別な考慮を要します。
建築請負契約は、一般的には破産時に解除されるものとなります。しかしながら、例えば工事が終盤にさしかかっている場合には、工事を終えて報酬を獲得した方が、債権者への配当に回せる金額が大きくなります。この点についても考慮しながら方針決定していくと、より良い手続が取れます。
仕掛工事の請負報酬について
また、仕掛工事の完成度によっては、請負報酬を一部請求できる場合があります(出来高払い)。この費用も、やはり破産手続や配当に回す金銭に充てられますから、各仕掛工事の進捗・状況にも注意を払うことが重要となります。
資材等の処分について
最後に、支給品・貸与品などの資材や、倉庫等に保管されている資材等の処分方法も問題となります。もちろん放置することはできませんので、同種の業者に販売できるのか、また、販売ができないのであれば処理にどの程度の費用がかかるのかなど、多くの検討を要します。
建設業・建築業の倒産・破産手続きの流れとポイント
破産申立ての流れと関係者の役割
破産申立ての一般的な流れと関係者の役割は以下のとおりとなります。
弁護士への相談と方針決定
まず、必ず弁護士への相談が必要になります。破産申立ては非常に多くの資料を整理して会社の状況を的確に把握することからスタートします。会社の収支状況・資産状況は当然のこととして、破産に至る経緯といったマクロの視点から、各建築資材の帰趨といったミクロの視点まで駆使して、会社の状況を整理し、これを裁判所に理解してもらえるように資料化するのです。
この作業は、必ず弁護士と共に行っていく必要があります。また、単純に「倒産」といっても、破産・民事再生・会社更生・私的整理など、多くの方法がありますし、場合によっては事業譲渡・株式譲渡などの手法を採用するべき場合もあります。これらの方針についても、弁護士と相談しながら決定していくと良いでしょう。
破産申立て前の準備と手続
方針が決定されたら、破産申立て前の準備と手続を進めていくこととなります。事業停止や従業員の解雇に加え、場合によっては取引先への通知・債権者への通知なども行う必要があるでしょう。
ちなみに、弁護士に依頼して弁護士から各債権者に通知を送ることとなった場合には、以後、債権者対応は全て弁護士が行うこととなります。このため、安心して破産準備に集中することができます。
破産申立ての準備ができたら、裁判所に破産申立書を提出します。
破産手続開始決定と破産管財人の選任
その後、裁判所が書類チェックを終えたら、破産手続開始決定がなされます。これと同時に裁判所は、会社の破産手続に際して、会社に回収可能な財産が残されていないか、会社に財産隠しがないかなどの点について確認するための弁護士(破産管財人)を選任します。
あなたは、破産について依頼した弁護士と共に破産管財人との面談を行い、破産手続のための調査に真摯に協力していくこととなります。
債権者集会の開催と配当手続き
破産手続中の調査結果等は、破産管財人によって裁判所・債権者に報告されます。この報告手続が債権者集会と呼ばれます。
債権者集会には、会社の資産状況・配当の有無について関心のある債権者が出席してくることもあります。あなたも、破産について依頼した弁護士と共に債権者集会に出席することとなりますから、出席した債権者から質問を受けた場合には、誠実に回答・対応する必要があるでしょう。
関連業者への適切な連絡方法
また、建設業・建築業の企業が破産する場合には、仕掛品の帰趨や、資材の処理など、関連業者に対して多数の連絡をとる必要があります。この際には、何らの戦略・方針もないままに社長が片っ端から連絡を取れば良いというものではありません。
この点も、弁護士と共に方針決定した上で、必要に応じて弁護士からの連絡も含めて丁寧に対応していくことが求められます。
破産手続をスムーズに進めるためのポイント
以上のように破産手続が進んでいきます。これらの手続をスムーズに進めるためには、会社倒産・法人破産事件になれた弁護士に依頼をすること、その弁護士の指示に従って破産管財人の調査等に誠実に協力することが重要といえるでしょう。
特に、会社財産を隠す・会社代表者のために利用するといった事態がないようにご注意ください。こういった行為は破産手続における調査を増やし、事件終了時期を延ばしてしまいますし、場合によっては、あなた自身の免責が認められなくなることもあります。
建設業・建築業の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリット
建設業・建築業の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
複雑な破産手続を弁護士に任せてしまうことができる
上記のとおり、破産手続は、専門家である弁護士以外からすると、非常に難解な手続となります。このような手続を自ら行うことは、事実上不可能といえるでしょう。
企業倒産になれた弁護士に破産手続を依頼してしまうことで、建設業・建築業の破産時に注意すべきポイントを押さえてもらい、安心して会社を閉めていくことができます。この点は大きなメリットです。
債権者対応を弁護士に一任し、ストレスから解放される
また、建設業者であれば、一度は、下請業者に工事代金を支払えず、毎日督促の連絡を受けた経験があるのではないでしょうか。下請業者も死活問題ですので、必死に債権回収をしようとしてきます。これらの督促は大変なストレスとなります。
弁護士に破産手続について依頼してしまえば、債権者からの連絡を全て弁護士に回すことができます。債権者からの督促に悩まれることから解放され、精神的に落ち着くことができるのも、弁護士に破産手続を依頼する大きなメリットです。
まとめ
以上のとおり、建設業・建築業における倒産時の注意点と手続についてご説明しました。ぜひ、建設業・建築業における倒産・破産についてお悩みの場合には、当事務所へのご相談・ご依頼をご検討ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014