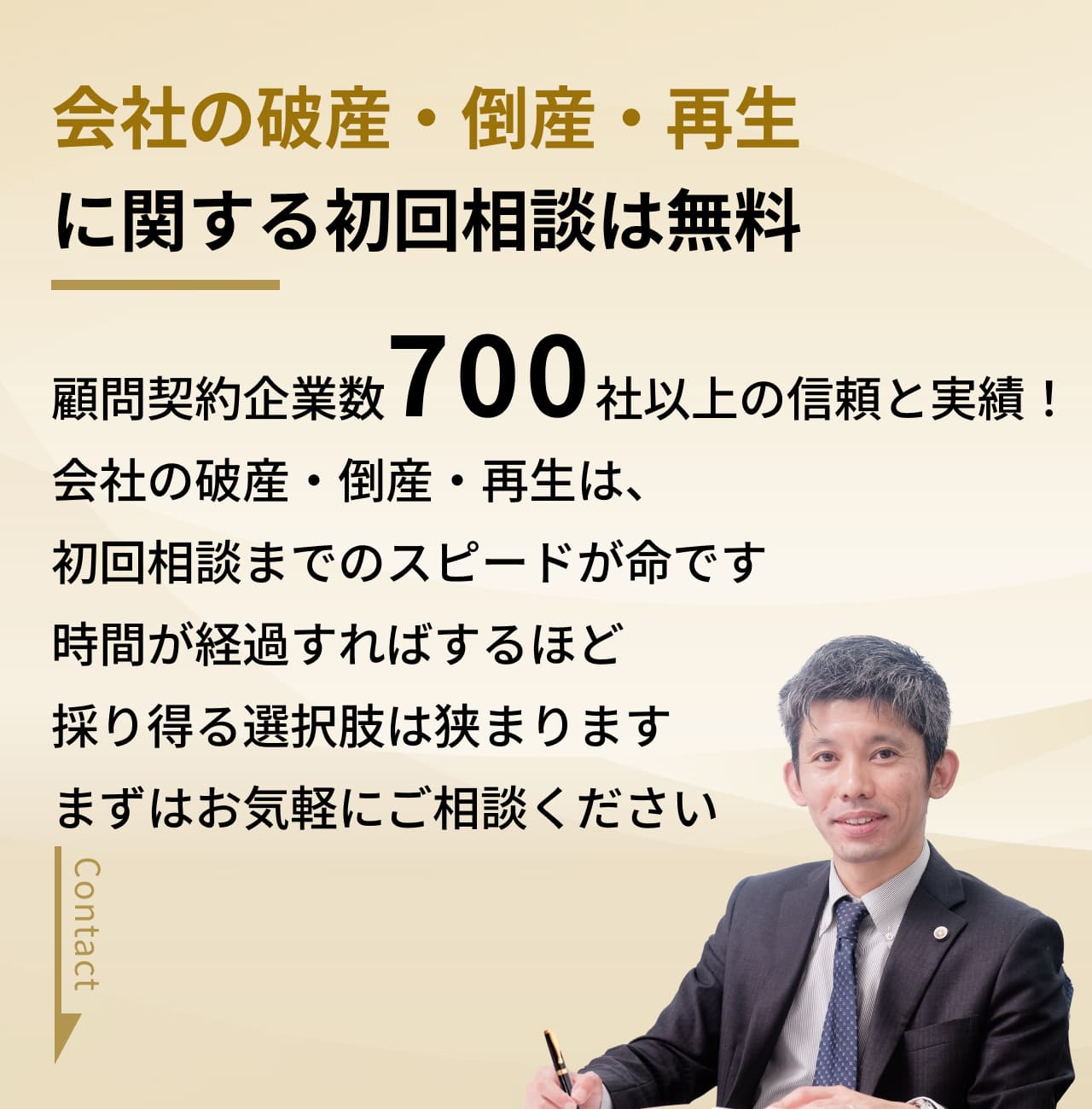目次
人手不足による倒産とは?最新の動向について
皆さまは、2025年初頭に帝国データバンクが、調査の結果、人手不足による倒産が2年連続で過去最多であったというニュースを公表したことをご存じでしょうか?2023年、2024年と、2年連続で人手不足による倒産件数が増えているようです。
業種・地域を問わず、全国的に人手不足による倒産件数が増えてきている背景には、深刻な原因が隠れています。以下では、人手不足による倒産への対策と破産手続の流れ・注意点についてご説明します。
どのような職種で増えている?
ちなみに、特にどのような職種で人手不足による倒産が増えているのでしょうか?
帝国データバンクが提供する情報によれば、建設業界・物流業界での倒産件数が半数程度を占めているようです。特にこれらの業界において、人手不足が深刻化しているといえるでしょう。
人手不足による倒産が起きる原因
それでは、人手不足による倒産が起きる原因についてご説明します。
採用コスト・人件費の増加による経営圧迫
まず、採用コスト・人件費の増加が挙げられます。昨今の物価高に煽られる形で、採用コスト・人件費が増加しています。
また、最近は、いわゆる働き方改革の影響が建設業・運送業にも及び始めたこともあり、会社がこれまで当然の前提としていたような長時間労働をさせることはできません。このため、同じ時間の労働を、より多い人数でカバーしなければならず、人件費自体がこれまで以上にかかってしまう状態となっています。
求職者の減少と採用難の深刻化
次に、求職者の減少と採用難の深刻化が挙げられます。
建設業・運送業を中心に、労働者の高齢化の問題が起きています。これは、若年者による求職者数が減っていることによります。働き方改革の波が押し寄せているとはいえ、未だに労働環境が厳しいと思われがちな業界は、就職活動から敬遠されてしまいがちです。
医療機関でさえ、いわゆる「直美」(医師国家試験合格後、直接、美容整形外科に就職すること)が流行っており、問題視されている状態です。
このような状況下で、採用担当者・人事担当者としても採用難に悩まされることとなっているのです。
離職率の上昇と人材の流出
更に、離職率の上昇と人材の流出の問題も挙げられます。
いわゆる転職エージェントや転職サイトのCMが多く流れるようになっているとおり、ここ数年は転職市場が活発に動いています。このため、従業員も比較的簡単に離職・退職してしまいがちとなり、人材の流出を止めがたくなってきています。
後継者不足による事業継続の困難
最後に、後継者不足による事業継続の困難化も挙げられます。労働者の高齢化のみならず、経営者の高齢化も問題となっているのです。
やはり、若年者や若手の従業員には、かつての終身雇用制度が一般的であった頃と異なり、会社と共に生きていくという視点は流行らないのかもしれません。それゆえに、会社の経営を継ぐ・会社内で出世して経営者になる、という考えを持つ従業員が減少しており、深刻な後継者不足に悩む方が増えています。
この問題も、会社の人手不足の問題の一つということができるでしょう。
黒字経営でも倒産の可能性はある
ちなみに、黒字経営でも倒産の可能性があることをご存じでしょうか。
黒字経営であったとしても、現預金等の流動資産が足りなかったり、まさに人手不足によって事業維持が困難になったりすると、倒産を選択せざるを得なくなることがあるのです。極端な話、多くの取引を受注して多額の利益を見込めたとしても、人手が足りなければ実際に利益を享受することはできません。
従業員の人手も、現預金同様に、事業維持のために必須であるといえることに、改めて注目しなければならないでしょう。
人手不足による倒産への対策
それでは、人手不足による倒産には、どのような対策を取れば良いのでしょう。
採用戦略の見直しと魅力的な雇用条件の提示
まず、採用戦略の見直しと魅力的な雇用条件の提示をするべきでしょう。
人手不足は、そもそも求職者を集めて採用することに苦労するからこそ起きてしまう問題ではあります。企業PRをしてその魅力を発信すると共に、雇用条件をアップして他社との差を付けるべきです。
従業員の定着率を高める施策(福利厚生・キャリアパスの明確化)
次に、従業員の定着率を高める施策として、福利厚生を充実化したり、キャリアパスを明確化したりすることも有用です。
転職者が相次ぐのは、今のままの勤務を続けることに将来の不安が伴うからといえるでしょう。例えば社内での資格取得制度を整備して昇給させるなどすれば、転職者・退職者が出ることを防ぐことも期待できます。
DXによる業務効率化
また、業務DX化による業務効率アップも有益な施策となります。
これによって従業員の負担を減らし、長時間労働をする必要がなくなれば、やはり転職者・退職者が減少するでしょう。現在は様々な業務DX化のツールがありますから、積極的な導入を検討するべきです。
外部リソースの活用(派遣・業務委託・フリーランス)
同様に、社内の従業員の負担を減らすために、外部リソースを活用することもお勧めです。
派遣業者・業務委託・フリーランスなどを活用し、社内の業務の一部を外部委託することで、人手不足を補うこともできます。こちらも、積極的な活用を検討するべきでしょう。
業種別の人手不足による倒産が発生するよくある事例
ちなみに、いわゆる2024年問題の影響を受けた以下の業種では、特に人手不足による倒産が多いようです。どのように人手不足が倒産に繋がるのか、よくある事例をご紹介します。
物流・運送業
まず、物流・運送業です。
これらの業種では、労働者一人ひとりの長時間労働に頼って多くの荷物を運ぶことによって利益が保たれてきました。しかしながら、個々の労働者の長時間労働が規制されたことにより、純粋に利益を上げることが困難になります。業務量と人手が合わなくなってしまっているのです。
この結果、従前のような利益を得ることができず、倒産に至ることが多いです。
建設業
次に建設業です。
建設業においては、従業員の高齢化・新人労働者獲得の難化により、労働者1人当たりの作業量が減ってきてしまっています。このために、工期どおりに各種工事を終わらせることができずに、外注業者・外部の職人に必要以上に頼らなければならず、工事に要する費用が増えてしまいます。
この結果、費用が増えてしまい、倒産に至る事例が増えています。
医療機関
最後に医療機関です。
医療機関においても、人手不足は深刻化してきているようです。特に看護師の人数不足により、一人ひとりの業務量が増加してしまったり、患者とのコミュニケーション不足が生じて余計なロスが生じたり、目に見えない部分での人的コスト増に繋がることとなります。
医療機関では機材投資などのコストが非常に大きいため、微妙な収支のバランスを崩すことにより、倒産への一途を辿る事例が増加しています。
人手不足による倒産・破産を検討する際の注意点
ここで、人手不足による倒産・破産を検討する際の注意点をご案内します。
事業継続と廃業の判断基準
まず、事業継続するのか廃業するのかの判断基準には注意が必要です。廃業する場合には、黒字だから事業継続・赤字だから廃業という基準ではありませんので、一度弁護士にご相談いただく必要があります。
取引先・金融機関・従業員への影響と対応策
次に、取引先・金融機関・従業員への影響と対応を、破産の決断をする前に決めておく必要があります。特に従業員は失業することとなりますから、適切な対応を取ることが必須といえます。
事前に弁護士・専門家へ相談することの重要性
これらの点について検討するためには、やはり弁護士への相談が重要です。企業倒産案件を数多く扱い、これに慣れた弁護士から的確な助言を受けるべきでしょう。
人手不足による倒産・破産手続の流れとポイント
人手不足による倒産・破産手続の流れとポイントについて、簡単にご説明します。
破産手続の流れ
破産手続は、以下のように流れます。
① 弁護士への相談→破産手続開始申立ての準備
企業が破産する場合には、弁護士への相談・依頼が必須です。弁護士が破産手続開始申立ての準備を手伝ってくれます。
② 破産手続開始決定・破産管財人選任
裁判所に破産手続開始申立てをすると、裁判所は破産手続開始決定を下すとともに、破産管財人を選任します。破産管財人は、破産する会社の財産状況等について調査を行います。
③ 換価・配当→破産手続終了決定
企業の財産を全て金銭化して債権者に配当すると、破産手続は終了します。
任意整理やM&A(事業売却)などの代替の検討
人手不足が問題である場合には、収支バランスを崩してしまって倒産するケースが多いので、任意整理やM&Aによって解決ができる場合もあります。いきなり倒産を選択するのではなく、ぜひ、弁護士と相談してみてください。
経営者が負う責任とリスクの整理
また、弁護士に相談する際には、必ず、弁護士と共に、経営者が負う責任とリスクを整理しましょう。その上で、代替案や人手不足解消のための施策をとることができないか、倒産以外の解決策も探してみることをお勧めします。
人手不足による倒産・破産を弁護士に相談するメリット
ここで、人手不足による倒産・破産を弁護士に相談するメリットをご紹介します。
法的手続のスムーズな進行
まず、法律の専門家である弁護士に手続を任せることができますので、法的手続がスムーズに進行します。破産手続においては、数多くの法律問題が生じます(破産手続は、法律問題のるつぼと呼ばれます。)から、必ず弁護士の助力が必要といえるでしょう。
債権者対応や取引先・従業員とのトラブル回避
次に、債権者対応を弁護士に任せることができ、取引先・従業員との無用なトラブルを回避できることもメリットとして挙げられます。弁護士がいなければ、債権者からの取立ての連絡がやまず、また、従業員からの突き上げにも遭うことになってしまうでしょう。
廃業後の再スタートの支援
更に、廃業後、経営者の再スタートの支援を受けることができる点も重要です。企業が倒産したとしても、経営者の人生は続きます。その際の再スタートも、弁護士の支援のもとに取り組むべき問題といえるでしょう。
まとめ
以上のとおり、経営者が「人手不足による倒産」について検討する時の対策と破産手続の流れ・注意点について解説しました。
人手不足による倒産を検討する際には、弁護士への相談が必須です。当事務所では、企業倒産案件を多く扱っております。お悩みの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014