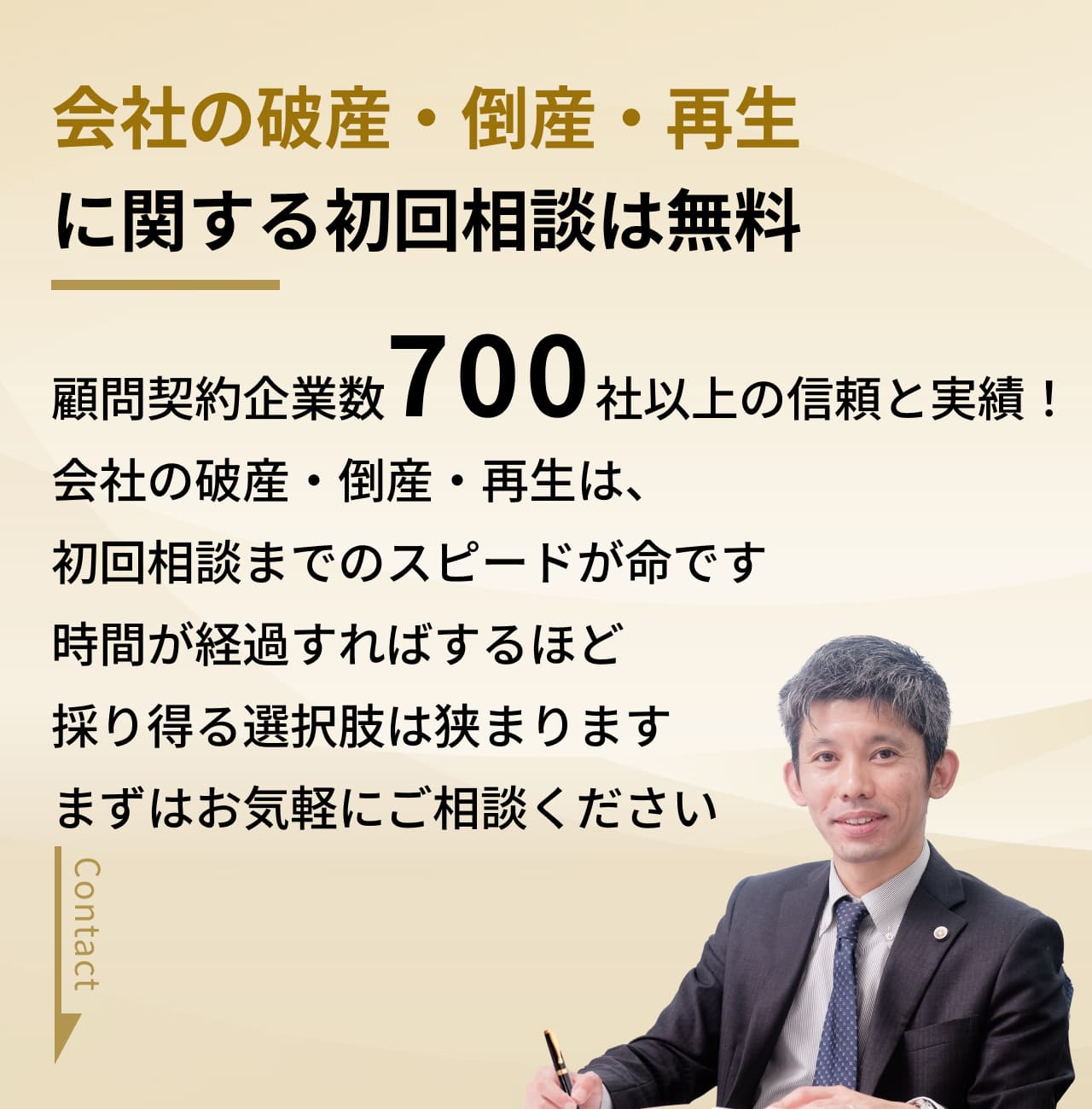少子化や競争の激化、オンライン教育の普及により、学習塾の経営環境は厳しさを増しています。「生徒のためにも塾を続けたいが、もう限界だ」と苦渋の決断を迫られている経営者の方もいるのではないでしょうか。
特に学習塾の場合、一般的な企業の倒産とは異なる悩みもつきものです。
- 生徒や保護者への説明や返金をどうすればいいかわからない
- 受験を控えた生徒の転塾サポートが心配
- 講師への給与支払いや解雇手続きが不安
もし、塾の倒産や破産を検討しているなら、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、学習塾には生徒の将来を守る責任があり、保護者対応や個人情報管理など法的義務も厳格だからです。
適切な手順を踏まないと、生徒や保護者、地域に大混乱を招きかねません。
本記事では、学習塾の倒産・破産手続きの流れや特有の注意点について、弁護士が詳しく解説します。最後までお読みいただければ、複雑な手続きへの理解が深まり、冷静な判断ができるようになるでしょう。
この記事でわかること
- 学習塾の倒産がおきる主な要因
- 生徒・保護者対応などの重要ポイント
- 破産手続きの具体的な流れ
- 弁護士に依頼するメリット
【記事のまとめ】
学習塾業界は、少子化や競争激化、オンライン教育の普及等を背景に倒産が増加しています。学習塾の破産手続きには、受験生を含む生徒の転塾先確保や授業料の返金対応、講師の雇用問題など、教育機関特有の配慮と迅速な判断が求められます。
自己判断での対応は、保護者とのトラブルや法的責任等のリスクを招くため、早期に専門家である弁護士の支援を受けることが不可欠です。弁護士に依頼することで、複雑な手続きや債権者対応を一任でき、生徒や従業員への影響を最小限に抑えた適切な整理が可能となります。円滑な解決のために、まずは弁護士法人グレイスへご相談ください。初回相談は無料です。
学習塾の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリット
2025年は、年始から学習塾の倒産のニュースが世間をにぎわせました。実は2024年は、学習塾の倒産件数が過去最多となった年でした。今、学習塾を経営されている方の中にも、様々な理由から破産・倒産をお考えの方も多いのではないでしょうか。
ここでは、まず、学習塾の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリットをご紹介します。
債務整理
まず弁護士にご相談をいただくと、破産・倒産のみならず、債務整理による解決という選択肢が出てきます。債務整理とは、いまある借金を分割払いで支払っていくことで借金の返済方法を整理することを指します。
弁護士と一緒に会社の資産・負債状況を確認すると、借金の種類・総額が分かりますので、あえて倒産を選択しなくても借金を分割払いにすることで事態が解決するかもしれません。
保護者への返金
また、倒産・破産に悩んでいる時期に、保護者に勝手に返金してしまうと、かえってのちの破産手続において、一部の方に返金したことが問題視されてしまうことがあります。この場合には、むしろ保護者を破産手続に巻き込んでしまう結果を招くでしょう。
適法かつ適切な保護者対応はどうすればよいのかという点についても、弁護士にご相談いただければ助言を得られるはずです。
従業員の解雇
従業員の解雇も、破産手続の進捗・進行を見定めながら行う必要があります。
従業員を解雇する際には、最後の給与を未払にして、解雇予告手当1か月分を支払うという対応をすることが多いです。これは、破産手続が開始したのち、労働者安全健康機構という期間が未払給与の一部を立替払いしてくれるからです。
この制度の内容については弁護士が専門家になりますから、弁護士からの助言がないと制度利用すら危ういでしょう。
自己破産・民事再生の申請サポート
また、実際に倒産を検討して自己破産や民事再生の申請を行う見込みとなった場合には、必ず弁護士のサポートを受ける必要があるでしょう。
裁判所に自己破産や民事再生の申立てをする場合には、膨大な資料から会社の資産状況・負債状況等を細かく記載した申立書を作成する義務を負います。更に自己破産時に不用意に財産が散逸しないように監督・指導することが必要です。
これらの申請サポートを得るためにも、弁護士に相談・依頼されることは重要でしょう。
M&Aや事業譲渡
学習塾業界は競争が激しく、ライバル企業が多い業態です。それゆえに、倒産の危機に直面した学習塾事業を買い取りたいと考えている企業も多く存在します。
塾に通う生徒の次の行き先を確保する意味でも、弁護士の協力を得ることができれば、のちの倒産手続において問題にならない形でのM&Aや事業譲渡を実施することもできる可能性があります。弁護士に依頼することで、選択肢を増やすことができるのです。
学習塾の倒産・破産が発生する要因
ちなみに、学習塾の倒産・破産が発生する要因としては、以下のようなものがあります。
少子化
まずは、少子化に伴う生徒数の減少です。単純に顧客数が減っていく現在、学習塾の経営は年々困難になっていっています。
競争の激化
次に挙げられるのが、競争の激化です。昨今は、学習塾業界は戦国時代の様相を示しており、数多くの新興塾ができています。少子化と相まって過剰競争になってしまっていることも倒産増加の要因です。
オンライン教育の普及
そしてこれらの要因に拍車を掛けているのが、オンライン教育の普及でしょう。現在は、拠点を持たずにオンライン教育の提供のみ扱う学習塾も増えてきており、旧来の学習塾の運営に見直しを余儀なくされています。
教育費負担の見直し
また、昨今は、過剰なまでに膨れ上がってきた教育費負担が見直されている時期でもあります。オンライン教育のみ提供する形で比較的安価な学習塾が展開される現在では、学習塾通学のための費用をそこまで支出しない家庭が増えてきていることにも納得でしょう。
学習塾の倒産・破産における注意点
このような要因が基となって破産に至る学習塾ですが、実際に倒産・破産する際には、以下のような点に注意を払うべきです。
生徒・保護者への対応
まず、最も重要なのが生徒・保護者への対応です。
授業料の返金対応
授業料の返金対応ができるかどうかは、弁護士とよく相談の上で決定するべき事項です。場合によっては、のちの破産手続において裁判所から返金行為を否定されるおそれがあり、かえって保護者をトラブルに巻き込むおそれがあります。
転塾のサポート
次に、生徒が転塾するために必要なサポートを尽くしてあげる点にも留意が必要です。できるだけ生徒の受験に影響がなく、かつ、転塾がしやすい時期を倒産時期として選択することができればベストです。
講師・従業員への対応
また、講師・従業員への対応も重要です。
給与
まず、給与を支払うことができるのか、一部遅配になってしまうのか、もはや全額支払えないのか。この点を正しく理解することができなければなりません。仮に給与を支払えない場合には、立替払いという制度を利用することも検討する必要があります。
退職手続
また、従業員を退職させる日にちを決定し、離職票の交付・健康保険等の脱退手続等の細かな作業を行う必要もあります。
テナントの解約手続
テナントについても、解約・明渡手続を行うことができれば丁寧です。
急に夜逃げ同然にテナントを離れざるを得ない、というほどに資金的な余裕がない状態になってからでは遅いので、ある程度資金の余力があるうちに、破産の準備に着手することが肝要です。
リース契約のある備品の処理
ちなみに、コピー機や電子黒板等のリース物品については、弁護士が各リース会社と連絡し、リース会社に引き取ってもらうのか、それとも廃棄するのか、細かな扱いを協議します。このため、リース物品を勝手に捨てたり売ったりしないように注意しましょう。
学習塾の倒産・破産手続きの流れとポイント
以下、学習塾の倒産・破産手続きの流れとポイントを簡単にご説明いたします。
破産申立ての流れと関係者の役割
破産申立ての流れは以下のとおりです。企業代表者と破産手続についての依頼を受けた弁護士との相互の協力・協議がなされることで、破産手続が進んでいきます。
弁護士への相談と方針決定
最初に、弁護士への相談が必須となります。破産申立てにおいては、極めて多数の情報・資料を分析して会社の資産・負債状況、収支状況を適切に把握することが必要といえます。この作業は弁護士による助力を得ながら進めるべきです。
また、一言で「倒産」といっても、破産・民事再生・会社更生・私的整理など複数の方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。更に、状況次第で、事業譲渡・株式譲渡などのM&Aと呼ばれるような手法を採用するべき場合もあります。こういった様々な法的方針について、弁護士と協議しながら進めていくと良いでしょう。
破産申立て前の準備と手続き
弁護士に相談して方向性が決まったら、破産申立て前の準備と手続に着手していくこととなります。破産申立て前の準備としては、事業停止、従業員の解雇、保護者への説明、子ども達の行き先提供など、学習塾として取り組むべき多数の手順があります。これらの手順をどのような順番で行うべきかについても、弁護士と考えていく必要があります。
なお、弁護士に依頼した場合には、弁護士からほぼ全ての債権者・取引先に通知を送ることとなりますので、それ以降、債権者・取引先の対応は弁護士が行うこととなります。
破産申立ての準備ができたら、管轄する裁判所に、破産手続に要する書類を提出することになります。
破産手続開始決定と破産管財人の選任
破産申立書の提出後、裁判所が同申立書の確認を終えると、破産手続開始決定が下されます。また、同時に裁判所は、企業の破産に関し、企業に換価可能な財産があるかどうか、企業が財産の隠匿をしていないかどうかなどを確認させるため、別途、弁護士を破産管財人に選任します。
企業代表者は、破産について対応してくれる弁護士と一緒に、破産管財人との面談を行うことになります。破産法上、企業代表者には、破産手続の調査に真摯に協力する義務を負いますので、注意が必要です。
債権者集会の開催と配当手続き
破産手続における破産管財人の調査の内容は、裁判所や債権者に報告されます。この報告のための手続は債権者集会と呼ばれ、裁判所で実施されます。
この債権者集会には、会社に残された資産の状況や、配当可能な財産の有無などに興味のある債権者・取引先が出席してきます。企業代表者も破産について対応してくれる弁護士と一緒に債権者集会に出席しますので、債権者から質問をぶつけられた場合には、誠実に回答・対応する必要があるでしょう。
破産手続をスムーズに進めるためのポイント
破産手続はこのように進みます。破産手続をスムーズに進めるためには、会社・法人の破産事件に慣れた弁護士に依頼することが必須となります。このような弁護士に依頼することができれば、破産管財人からの指示にも的確に応えることができるでしょう。
まとめ
以上のとおり、学習塾における倒産時の注意点と手続についてご説明しました。当事務所には、法人の倒産・破産について数多くの案件を手掛けた確かな実績があります。学習塾経営者の方で倒産等にお悩みの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014