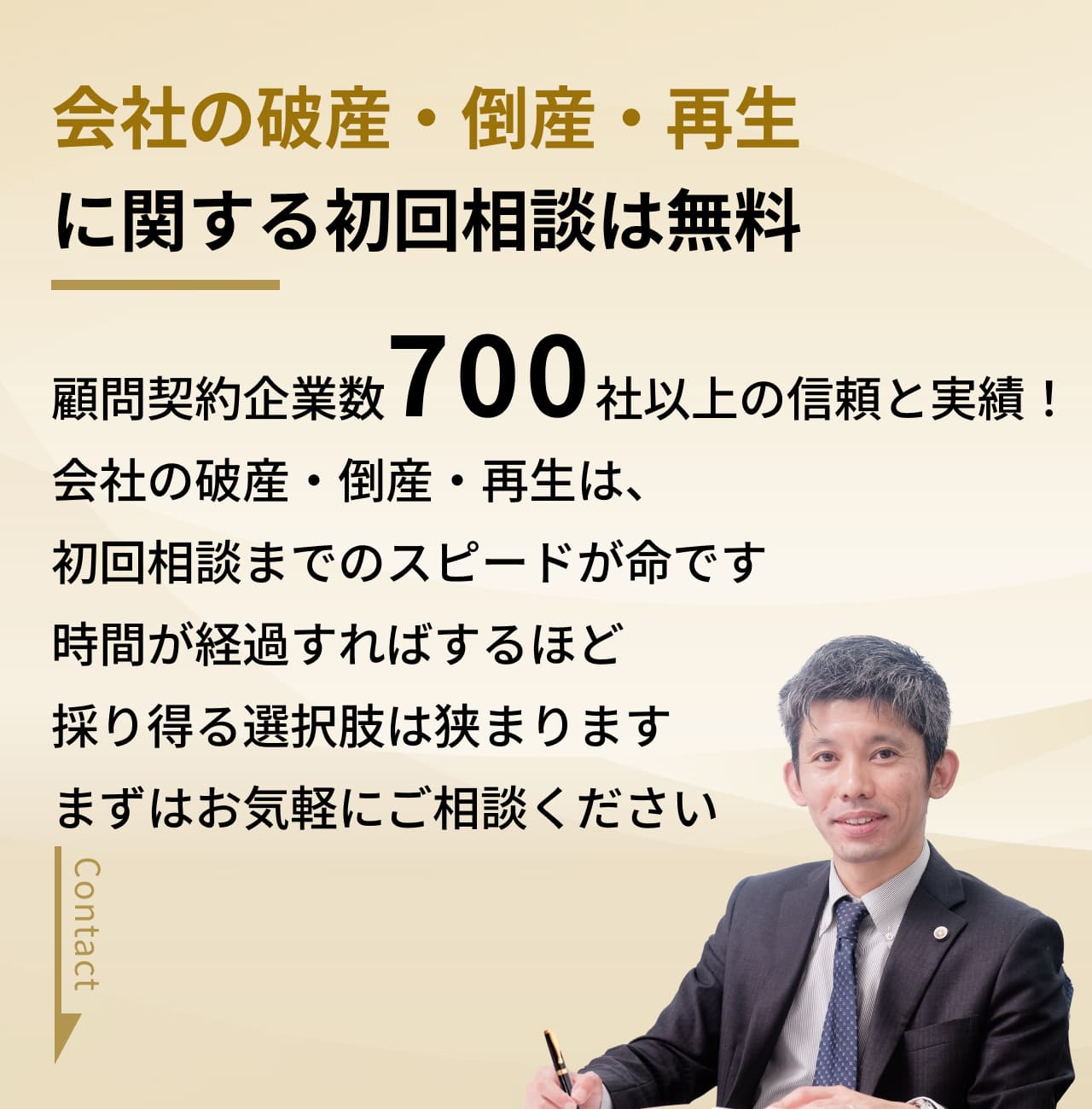昨今、肥料や飼料の高騰、後継者不足に加え、天候不順による不作も重なり、農業経営はかつてない苦境に立たされています。「代々続いた農地を守りたいが、もう限界だ」と、廃業を考えている方もいるのではないでしょうか。
特に農業の場合、一般的な事業の倒産とは異なる悩みもつきものです。
- 農地法などの規制があり、土地の処分が難しい
- 家族が連帯保証人になっており、生活への影響が心配
- 農機具や家畜の処分方法がわからない
もし、離農や破産を検討しているなら、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、農地の処分には農業委員会の許可が必要なほか、補助金の返還義務が生じるケースもあり、専門的な判断が不可欠だからです。
適切な手順を踏むことで、家族への負担を最小限におさえられます。
本記事では、農業の倒産・破産手続きの流れや特有の注意点について、弁護士が詳しく解説します。最後までお読みいただければ、複雑な手続きへの理解が深まり、再出発に向けた見通しが立つようになるでしょう。
この記事でわかること
- 農業の倒産がおきる主な要因
- 農地や家畜の処分など特有の注意点
- 破産手続きの具体的な流れ
- 弁護士に依頼するメリット
【記事のまとめ】
農業経営は、資材高騰や後継者不足、天候不順等が重なり、非常に厳しい局面を迎えています。農業の破産手続きには、農地法に基づく農地の処分制限や補助金の返還問題、家族が連帯保証人となっている場合の生活再建など、一般企業とは異なる複雑な課題が山積しています。
これらを自己判断で処理しようとすると、法的なトラブルを招き、再出発が困難になるリスクがあります。早期に弁護士へ依頼することで、農協や債権者との交渉を一任でき、精神的な負担も大幅に軽減されます。家族や従業員への影響を最小限に抑え、適切な解決を図るために、まずは弁護士法人グレイスへご相談ください。初回相談は無料です。
農業の倒産・破産が発生する要因とは?
いわゆる新型コロナウイルス感染症の影響が薄れつつある2024年・2025年は、倒産件数が増加している年でもありました。2024年には、農業の倒産件数が過去最多となったということもニュースで取り上げられています。
農業の倒産・破産が発生する要因の代表例は、以下のようなものとなります。
高齢化と人手不足・後継者不足
まず、農業という業界・業態全体を襲う高齢化・人手不足・後継者不足という問題です。
農業は一般に、大変な労働を伴う・収入が安定しないといったイメージを持たれています。このため、生産者に生まれた子どもたちも農家を継がないという後継者不足の問題が深刻化しています。それゆえに、農業業界全体を高齢化・人手不足の問題が覆っているのです。
こうなってしまうと利益が上がりにくくなってしまい、倒産・破産に繋がります。
燃料と飼料の高騰
次に、燃料と飼料の高騰の問題も挙げられます。
昨今の物価高の影響を受け、燃料や飼料といった家畜を育成・生産する上で必要なものの高騰が激しくなっています。これによって農業の経費率が増え、その経営を圧迫するようになってきています。農家は燃料も飼料も非常に多く扱うこととなりますから、単価上昇の影響を強く受ける業態といえます。
天候・災害による収穫不良
更に、天候・災害による収穫不良とこれによる収入減少の問題があります。
地球温暖化の影響もあり、日本の気候は大きく変わりつつあります。ゲリラ豪雨や、例年の数値を超える暑さが当たり前の状態となってきている上に、真逆の冷害(冷夏)も発生しがちです。このような天候の変化・災害による収穫不良は、ダイレクトに農家の生産量を減らし、売上げ減少を招きます。
設備投資の高騰や借入金の返済負担
また、設備投資の高騰・借入金の返済負担も農業の倒産・破産件数増加の一要因でしょう。
いわゆるゼロゼロ融資の返済が始まってからは、農業に限らず、各種業界・業態での資金繰りの難しさが際立つようになってきました。加えて農業器具・車両等の設備投資費用に要する金額も高騰してきています。
これらの要因によってキャッシュフローに余力が無くなり、倒産・破産の途を選択せざるを得なくなっている農家が増えてきているのです。
農業の倒産・破産における注意点
それでは、農業ならではの倒産・破産における注意点をご紹介していきます。
個人事業主か法人かで対応が異なる
まず、個人事業主か法人かで対応が異なってくる点に注意が必要です。
法人であれば、倒産・破産によって法人が無くなってしまいますから、あまりややこしいことは起きません。
これに対して農家が個人事業主である場合には、農業についての廃業届を税務署に提出したり、保有している農地(畑や田など)の処分方法を検討したりする必要がでてきます。倒産・破産によって個人自体が居なくなるわけではありませんから、その後の生活をどのように立てていくのか、次の職業も含めて検討してから破産申立てをする必要があるでしょう。
農地や設備の処分・取り扱い
次に、農地や設備の処分・取り扱いの問題も農業ならではです。
農地は、農業委員会の許可がなければ、農業従事者以外に売ることができませんし、農地以外の用途に用いることもできません。また、農業設備は、まさに同種の事業を営む者でなければ全く価値を見出せないものであることが大半でしょう。もちろん、破産手続をとるのであれば、農業設備を勝手に破壊したり売却したりしてはいけません。
これらの処分のためには、例えば近隣の農家に農地や農業設備を買い取ってもらう(事実上の事業譲渡をする)などの対応が必要となるかもしれません。
連帯保証人や家族への影響について
また、連帯保証人や家族への影響が出やすいのも農業の破産ならではです。
農業は家族や親族が協力して行うことが多いです。この関係で、家族が事業用の借入れの連帯保証人になることも多いです。
更に、農業が倒産・破産する場合には、家族の収入全体に対する影響も大きくなります。家族経営の会社が倒産する場合と同じように、家族全員の収入がなくなってしまうということですね。このため、倒産手続を取る前に、家族の収入源について検討を加えておく必要があります。
補助金・助成金の返還の可能性がある
農業のために得た補助金・助成金の返還が必要となる可能性もあります。
この場合には、補助金・助成金の返還債務を破産手続にて処理できるのかどうか、法的観点からの検討を要しますから、弁護士の協力が必要不可欠になるといえるでしょう。
農業の倒産・破産手続きの流れとポイント
ここで、農業の倒産・破産手続の流れとポイントをご紹介します。
破産を検討すべきタイミング
まずは農業の破産を検討すべきタイミングについてご紹介します。そもそも破産手続を行うためには、弁護士費用・裁判所へ納める手続費用として、数百万円を要します。
このため、ある程度借金問題・多重債務問題に悩んでいるにしても、数百万円のキャッシュ(現預金)を確保した段階で破産するかどうかを決めておく必要があります。これを超えて、キャッシュがほとんどなくなってしまった後に破産をしようと決めたとしても、費用が捻出できなければデッドロックに陥ってしまいます。
キャッシュを失う前に、破産の決断をしましょう。
弁護士への相談
上記のようなタイミングで弁護士に相談することとなります。
個人事業主にせよ法人にせよ、破産手続を申し立てるためには、弁護士への依頼が必要不可欠です。破産手続に慣れていて信頼できる弁護士を見つけることに注力しましょう。
当事務所へのご相談を、ぜひお待ちしております。
家畜や作物を含めた財産・債務の整理
その後、弁護士との間で、家畜・作物等の財産の整理や、債務(買掛金・借入金)の内容・金額の整理を進めることとなります。
ここで整理した内容を前提に、その後の破産手続の進行の仕方を決めていくことになります。また、ここで、従業員の解雇や、農地・農業設備の整理の方法も決めていくことになります。
膨大な資料を整理しながら農業事業の実態について正確に理解していくことが、その後の手続を適切に進めるために必要となります。
申立書類の準備
上記の整理した情報を、破産手続申立書に記載していきます。
裁判所への破産申立て
申立書類の準備が済んだら、裁判所に破産手続の申立てをすることになります。破産手続を申し立てると、裁判所による書面審査が入ります。
審査の結果、破産手続開始の要件があると認めた場合には、裁判所は、破産手続開始決定とともに、破産管財人の選任決定を下します。
破産管財人による財産の管理・換価
破産管財人とは、破産手続が進む中で、破産者の財産を現金化して配当したりするなど、破産者の財産の管理処分権を持つこととなる弁護士を指します。この破産管財人は、裁判所が選びます。
債権者集会と配当手続き
破産管財人による財産調査・換価が進むと、債権者集会という裁判所の手続で債権者に破産者の財産状況が報告され、財産が多く残っている場合には配当手続がなされることとなります。
農地の扱いや農協との関係整理
破産手続中の換価手続の中では、農地の現金化や、農協との関係整理を進めていく必要があります。この場合には、破産手続申立てを行った弁護士と破産管財人が適宜の協力をすることとなります。
農業の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリット
農業の企業が破産・倒産をする場合には、弁護士に相談することが必要不可欠となりますが、この場合のメリットもご紹介しておきます。
状況に応じた最適な法的手続きの提案
まずは、法律専門家の手を借りることとなりますから、状況に応じた最適な法的手続の提案を受けることができるでしょう。
場合によっては、破産ではなく、事業譲渡等の手続を取るべき場合もあります。
債権者や農協との交渉のサポート
次に、債権者や農協との関係整理の際の交渉のサポートを得ることができる点もメリットになります。
やはりどうしても人間関係が絡む事項ですから、弁護士に交渉を任せてしまうことで、精神的負担が大きく軽減するでしょう。
財産や生活の再建に向けたアドバイス
更に、財産や生活再建に向けたアドバイスも期待できます。
代表者個人のその後の人生再建に寄り添う弁護士に依頼することが重要です。
家族や従業員への影響を最小限に抑える対応
最後に、家族・従業員への影響を最小限に抑える対応もしてもらうことができるでしょう。
事業・企業を廃業する場合には、やはりこれまで協力してくれた方への悪影響は抑えてあげたいところです。この点に関しては、ぜひ破産になれた弁護士のフォローを受けることをお勧めします。
まとめ
さて、以上のとおり、農業・農家の倒産・破産についてご説明しました。
当事務所では、多くの企業倒産案件を手がけた確かな実績があります。当事務所にご依頼いただければ、必ず満足いただけることと考えております。倒産等をお考えの農業の方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014