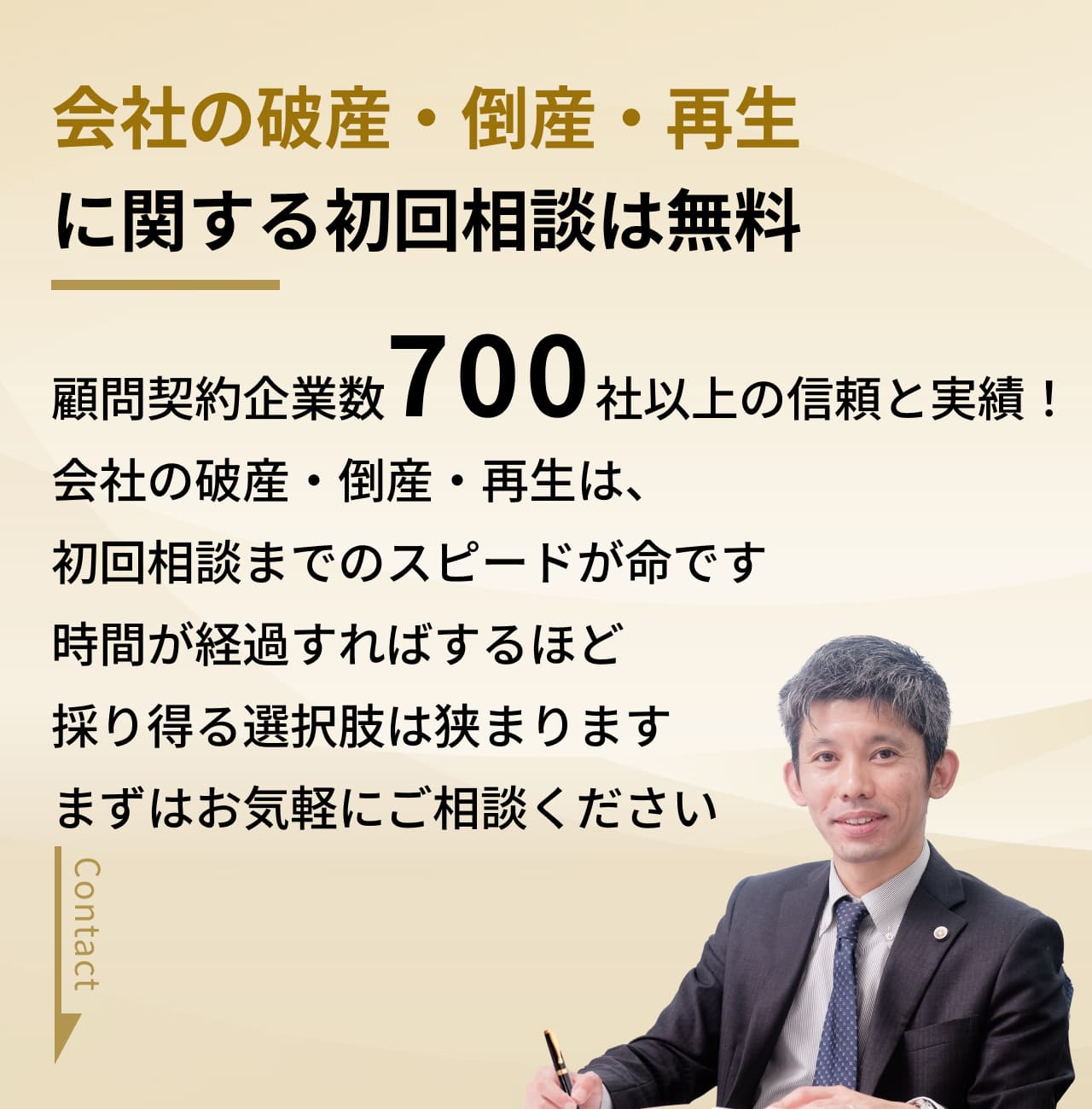昨今、原材料や燃料費の高騰、深刻な人手不足により、製造業の経営はかつてない厳しい状況におかれています。「いいモノを作れば売れる時代ではない」と、資金繰りに悩み、事業継続を諦めかけている経営者の方もいるのではないでしょうか。
特に製造業の場合、一般的な業種とは異なる悩みもつきものです。
- 高額な機械や工場の設備をどう処分すればいいかわからない
- 在庫の原材料や製品の扱いが不安
- 長年働いてくれた従業員の再就職先が心配
もし、会社の倒産や破産を検討しているなら、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、製造業は設備や在庫の売却、M&Aによる事業譲渡の可能性など、専門的な判断が求められる場面が多く、早期の決断が結果を大きく左右するからです。
適切な手順を踏むことで、混乱を最小限におさえることができるでしょう。
本記事では、製造業の倒産・破産手続きの流れや回避策、注意点について、弁護士が詳しく解説します。最後までお読みいただければ、複雑な問題が整理され、次の一歩を踏み出す勇気がわいてくるはずです。
この記事でわかること
- 製造業が倒産する主な要因
- 倒産を回避するための対策
- 破産手続きの具体的な流れ
- 弁護士に依頼するメリット
【記事のまとめ】
製造業は、原材料費やエネルギー価格の高騰、人手不足などの影響を受け、経営環境が急速に悪化しています。製造業の破産手続きでは、工場や機械設備の売却、在庫製品の処理、従業員の解雇対応など、専門的かつ迅速な判断が求められます。また、早期であればM&Aによる事業譲渡の可能性も検討できます。
自己判断での対応は、資産価値の毀損や法的トラブルを招くリスクがあるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。弁護士に依頼することで、複雑な手続きや債権者対応を一任でき、経営者の再出発に向けた負担も大幅に軽減されます。最善の解決策を見つけるために、まずは弁護士法人グレイスへご相談ください。初回相談は無料です。
製造業の倒産を避けるには
2024年は新型コロナウイルス感染症の影響が薄まったものの、いわゆるゼロゼロ融資の返済開始や、各種物価高の影響などの原因により、一気に倒産する企業が増えた年でもありました。
その中でも、製造業の倒産件数が増加傾向にあります。最近は何ら外部的な兆候を示さずに赤字経営に突入して資金繰りが上手くいかないまま倒産する企業も増えています。以下では、製造業の倒産を避ける方法と、仮に倒産・破産を選択する場合の流れについてご説明します。
資金繰りを安定させる
まず倒産を避けるために最も重要なのは、資金繰りを安定させることでしょう。
製造業の場合には、一定の売上は上がるものの、物価高などの影響で実際の利益率が維持できない場合もあります。また、突発的な海外情勢のあおりを受けて輸入・輸出における向かい風を受けてしまうこともあります。
これらの問題に対応しながら経営を維持できるように、資金繰り・キャッシュフローを安定させることに注力しましょう。
コスト管理を徹底する
次に、コスト管理を徹底することも倒産を避けるために重要な着眼点になります。
上記のとおり、物価高・人件費高騰の流れは勢いを増すばかりで、なかなか短期的な情勢回復は見込めていません。こうなると、徹底したコストチェック・コスト削減の取組みがなければ利益が上がりません。
特に最近はICT技術の成長も著しいので、設備投資をして定常的な人件費を抑えることなどを検討することは有用でしょう。
M&Aを検討する
また、最終的に倒産を避けて従業員の生活を守るためには、M&Aも検討対象になってきます。
経営者の経営権は失われたり弱まったりしますが、企業を生かすことはできますから、最終的な手段として検討の余地があるでしょう。但し、この場合には、法的なチェックポイントが多数あり、また、様々なリスクもあるため、弁護士の助言・助力が必須といえます。
倒産することのメリット・デメリットも含め、M&Aについては弁護士にご相談をなさってから決断・実行に移すことをお勧めいたします。
製造業の倒産・破産が発生する要因とは?
ちなみに、製造業の倒産・破産が発生する要因はどこにあるのでしょうか?主として、以下のような理由に基づくことが多いようです。
支援の打ち切り
まずは国や地方公共団体による支援が打ち切られていることが一大要因でしょう。
新型コロナウイルス感染症蔓延時は国をあげて事業維持・倒産防止のための各種援助がなされていましたが、これが落ち着いてから、各種支援が無くなってしまっています。更には、ゼロゼロ融資の返済までスタートしてしますから、企業としては苦しい状況です。
それゆえに資金繰りが上手くいかなくなって倒産する企業が増加しているのです。
物価高
次に要因として挙げられるのが、物価高です。
ここ数年で加速している物価高の影響は、原材料高騰、燃料費高騰、人件費高騰など、各種の余波を及ぼしてきています。それでも製造業者は製造物の価格を大きく引き上げることができませんから、企業としては単純に利益が減少する結果に見舞われます。
今般の物価高は解消の見込みが立っていない点にも問題の重さがあります。一時的な物価高であれば、なんとか追加融資等を得ながら経営を続ける方針も取り得ますが、この目途が立ちにくいのです。
人手不足
また、人手不足も製造業の倒産が起きる要因になっています。
当然ながら、人手が不足すると、製造業者の製造量は減少し、売上自体も減少してしまいます。しかしながら昨今は、各業態において、人件費高騰の問題に加え、タイパ・コスパを重視する世代の従業員を獲得することに非常に苦労している現状があります。最近は求人誌に比較的高めの収入を標記しても、それだけでは社員を獲得することができない時代になってきてしまっているといえます。
それゆえに、製造業者は倒産の選択をせざるを得ない状態に追いやられてしまっています。
製造業の倒産時の流れ
それでは、いざ倒産・破産する場合の流れについてもご紹介します。
倒産の決断
まずは経営者・経営層による倒産の決断が必要となります。
会社の現状を踏まえ、最後の決定的判断をせざるを得ないタイミングか、M&Aによる解決など他の選択肢も踏まえながら協議・検討することとなります。
弁護士へ相談
次に、倒産を決断した場合には、弁護士に相談することとなります。法人・企業体が破産する場合には、弁護士の協力は必須となります。
ここでは、ぜひ法人の破産案件を手がけている経験値のある弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
倒産手続
弁護士に相談・依頼したのちは、破産手続の申立て・裁判所への提出書類の作成に移ります。膨大な資料を弁護士が精査した上で、会社の現状・資産状況などを書面にまとめていきます。
この際には、平時付き合いのあった社会保険労務士さんや税理士さんの協力を要することもありますから、弁護士にご相談いただく際にはどの方にご依頼をされていたかなどもお伝えいただくとスムーズです。
これらの準備が整った段階で、裁判所に破産の申立てをすることとなります。裁判所は、破産手続開始決定と共に、破産管財人選任決定も下します。破産管財人とは、倒産した会社の財産状況を調査し、残った財産を全て現金化して配当処理する弁護士となります。
機械や在庫の売却
破産管財人は、製造のための機械や在庫品が残っている場合には、これらを売却することとなります。この際には、競業会社などがいますと、機械にせよ在庫品にせよ、比較的簡単に売却ができます。買い手に心当たりがある場合には、弁護士又は破産管財人に伝えましょう。
従業員の解雇
更に、従業員の解雇も行う必要があります。
一般的には、破産手続申立て前の一定の日を解雇日として事前に決めておき、その日に一斉に解雇を行うこととなります。この際には、離職票の作成や、住民税の普通徴収への切替え手続、保険証の切替え手続等も必要となります。
従業員数が多いほど、手続が煩雑になりますから、弁護士の協力を得ながら手続を進めていきましょう。
製造業の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリット
ここで、製造業の企業が破産・倒産する場合に弁護士に相談するメリットをご紹介します。
倒産手続をスムーズに進められる
まず、倒産手続をスムーズに進められる点がメリットになります。
特に法人破産になれた弁護士に依頼できれば、見通しも正確に立つため、安心することができます。
経営者の個人責任を軽減できる
次に、経営者の個人責任を軽減できる場合がある点も弁護士に相談するメリットです。
経営者の保証債務については、経営者保証ガイドラインと呼ばれる業界ルールが存在したりします。これらの手続を利用しながら経営者の破産を防ぐことができる場合もありますから、ぜひ弁護士の助力を得ましょう。
債権者・取引先とのトラブルを防げる
また、弁護士に依頼すれば、債権者・取引先とのやり取りは、以後弁護士が行うことになりますから、各種のトラブルを防ぐことができます。
この点も精神的な安心に繋がりますから、大きなメリットといえるでしょう。
M&A(事業譲渡)による事業継続の可能性
更に、弁護士に相談することで、倒産によらずにM&Aによる解決を図れる場合もあります。従業員の立場を守ることができることに繋がるので、積極的に検討したいところです。
まとめ
以上のとおり、製造業の倒産についてご説明しました。当事務所は法人専門で倒産処理を行う事務所です。ぜひ、お困り・お悩みの際には、当事務所に一度ご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014