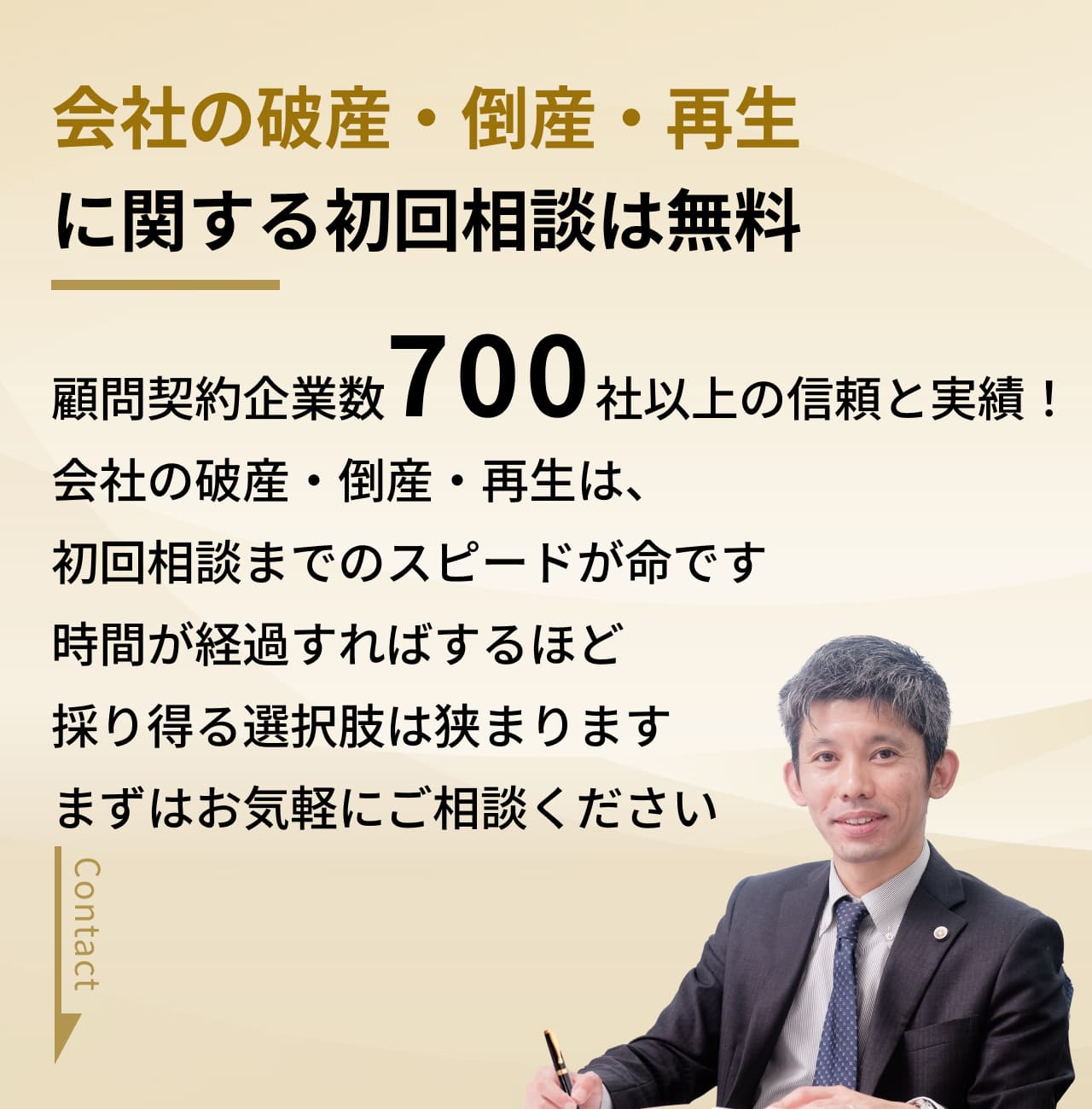昨今、原材料費の高騰や深刻な人手不足、ゼロゼロ融資の返済開始により、飲食業界はかつてない厳しい状況におかれています。「お店を守りたいが、もう限界だ」と苦渋の決断を迫られている経営者の方もいるのではないでしょうか。
特に飲食業の場合、一般的な業種とは異なる悩みもつきものです。
- 食材やアルコールの在庫をどう処分すればいいかわからない
- 従業員の解雇や未払い給与の対応が不安
- 店舗の原状回復や厨房機器のリース契約の解除への対応策がわからない
もし、お店の倒産や破産を検討しているなら、一刻も早く弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、飲食業は消費期限のある食材の処理や、高額な厨房機器のリース対応など、スピードと専門的な判断が求められる場面が多く、判断の遅れが大きなトラブルを招くからです。
適切な手順を踏むことで、混乱を最小限におさえられます。
そこで、飲食業の倒産・破産手続きの流れや特有の注意点について、弁護士が詳しく解説します。最後までお読みいただければ、複雑な問題が整理され、冷静に次の行動を選択できるようになるでしょう。
この記事でわかること
- 飲食業が倒産する主な要因
- 食材ロスやリース処理など特有の注意点
- 破産手続きの具体的な流れ
- 弁護士に依頼するメリット
【記事のまとめ】
飲食業界は、原材料費の高騰や人手不足、融資返済などが重なり、経営環境が急速に悪化しています。飲食店の破産手続きには、消費期限のある食材の処分、厨房機器のリース契約の解除、店舗の原状回復など、迅速かつ専門的な対応が求められる課題が山積しています。
これらを自己判断で処理しようとすると、資産価値を損なうだけでなく、取引先や従業員とのトラブルを招くリスクがあります。早期に弁護士へ依頼することで、複雑な手続きや債権者対応を一任でき、精神的な負担も大幅に軽減されます。リスクを抑え、適切な解決を図るために、まずは弁護士法人グレイスへご相談ください。初回相談は無料です。
飲食業の倒産・破産が発生する要因とは?
新型コロナウイルス感染症が落ち着き始めた2024年は、他方で、倒産件数が非常に多くなる年ともなりました。中でも飲食業者の倒産・破産件数は、2024年が過去最多となっています。やはり新型コロナウイルス感染症蔓延中の借金増加により、資金繰りが厳しくなって閉店・廃業する店舗が相次いでいるのです。
そもそも飲食業の倒産・破産が発生する要因はどこにあるのでしょうか?
コロナ後の需要の変化
まず、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外食需要は大きく変動しました。特に夜間の外食需要は驚くほど減ってきています。やはり、新型コロナウイルス感染症蔓延中の休業要請や時短営業を皮切りに、消費者の内食志向への変化、リモートワークの普及などが、多くの飲食店に打撃を与えているといえます。
現在でも、このような消費者の行動様式は完全に元には戻らず、需要の回復が鈍い店舗も少なくありません。
物価・光熱費・人件費の高騰
次に、食材の仕入れ価格、電気・ガス料金などの光熱費、従業員の人件費の高騰が挙げられます。世界情勢や為替変動の影響を受け、これらの費用は軒並み高騰しています。近年は、最低賃金の上昇や人材確保のための競争激化により、人件費も増加の一途をたどっています。
これらのコスト・経費増は、原価率を引き上げる結果を招き、飲食店の利益を圧迫する大きな要因となっています。
人手不足
最後に、人手不足の問題を指摘することもできます。ご存じのとおり、飲食業界は慢性的な人手不足に悩まされています。特にコロナ禍で離職した従業員が戻らず、新たな人材の確保も困難な状況が続いています。最近は外国人従業員を雇う飲食店も増えてきましたが、コミュニケーションのミスマッチに悩まされる経営者が多いようです。
人手不足は、サービスの質の低下や営業時間の短縮を招きますから、売上減少の悪循環を引き起こす原因となります。
飲食業の倒産・破産における注意点
さて、それでは、飲食業ならではの倒産・破産における注意点をご説明します。
在庫の把握と管理
まず、在庫の把握と管理に注意が必要です。どうしても食材は生鮮品が多く、消費期限があります。破産手続開始前に可能な限り使い切るか、適切な方法で処分する必要があります。また、アルコール類などの在庫も正確に把握し、破産管財人への引き継ぎ準備を進めなければなりません。
単純に廃棄してしまったり無償で譲渡したりする不適切な処分は、後々問題となる可能性がありますから、逐一弁護士と相談しながら進めましょう。
店舗の賃貸借契約の整理
次に、店舗の賃貸借契約の整理にも注意が必要です。通常、賃貸借契約には解約予告期間が定められていますから、その間の賃料も発生しますし、原状回復義務に伴う高額な費用が発生するケースも少なくありません。敷金や保証金の返還についても、原状回復の範囲・内容と共に、賃貸人との交渉が必要となります。
従業員への対応
また、サービス業の宿命ではありますが、従業員への対応には細心の注意を払う必要があります。やはり弁護士と相談しながら、解雇の時期、未払給与、解雇予告手当、退職金などの精算を、法的に適切に行う必要があります。
更に、従業員の社会保険の各種切替え手続や、離職票の交付など、解雇に応じて必要となる事務処理が一気に生じる点にも留意しなければなりません。
仕入れ先との取引関係の整理
破産申立て前に、仕入れ先との取引関係を整理しておく必要もあります。食材や飲料、消耗品などの仕入れ先に対する未払金がある場合、公平な対応が求められます。特定の仕入れ先だけを優先して支払うことは、破産法上の「否認」の対象となる可能性があり、のちに支払った金額の返還を求められる場合があります。
金融機関・保証協会との関係
金融機関・保証協会との関係を維持しておくことも大切でしょう。金融機関からの借入金や、信用保証協会の保証が付いている債務がある場合、破産手続においてこれらの債権者への対応は特に重要です。
経営者個人が会社の債務を連帯保証している場合は、法人の破産と同時に経営者個人の破産も検討する必要があります。この場合には、経営者保証ガイドラインも踏まえて検討をしていくこととなります。
飲食業の倒産・破産手続の流れ
次に、飲食業の倒産・破産手続の流れを簡単にご紹介します。
廃業準備・営業停止
まず、資金繰りが限界に達する前に、早めに閉店の準備を始めることが重要です。閉店のためには、在庫の処分、リース物品返却の手配、従業員への説明と解雇手続、賃貸人への連絡などの準備を行う必要があります。
破産にかかる資金の準備
廃業準備をしながら、現金をできる限り手元に残し、破産申立て費用や未払給与の支払いに充てられるよう、弁護士に相談しながら計画的に進めることが肝要です。
破産手続を進めるためには、弁護士費用や裁判所に納める予納金(主に破産管財人の報酬など)が必要です。最低でも百万円単位の現預金がないと、そもそも破産手続を行うことすらできません。経営者の手元資金や、事業の売上金などを適切に管理し、破産費用を捻出できるように準備していかなければなりません。
弁護士へ相談・依頼
これらの準備のために、経営悪化を認識した時点で、できるだけ早く弁護士に相談するべきです。
弁護士は、会社の状況を詳しくヒアリングし、破産以外の選択肢(事業再生など)も含めて最適な解決策を提案することができます。また、弁護士に依頼をすると、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付し、直接の取立て連絡を止めることができます。これにより、経営者は精神的な負担から解放され、破産手続の準備に集中できます。
破産手続
弁護士は、会社の財産状況、債務状況、事業開始から廃業までの経緯などを詳細にまとめた破産申立書を作成し、この書類を裁判所に提出して破産手続開始の申立てを行います。
裁判所が破産手続開始を決定すると、破産管財人が選任され、会社の財産調査、換価(現金化)、債権者への配当などを行います。概ね3か月スパンで債権者集会が開催され、裁判所において手続の進捗状況が報告されていくこととなります。
免責許可決定
法人の破産手続が終結して配当などが完了すると、法人格は消滅します。
一方、法人の経営者が会社の債務を連帯保証している場合は、別途個人の自己破産手続が必要となります。飲食店の場合は、銀行からの借入れを連帯保証していることが通常でしょう。別途、個人の自己破産手続が進み、裁判所から「免責許可決定」が出されれば、代表者個人の残りの債務の返済義務が免除されることとなります。
飲食業の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリット
ここで、飲食業の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリットも簡単にご説明します。
債務整理の選択肢を整理できる
まず、飲食店の実際の経営状況を弁護士が客観的に分析し、破産以外の事業再生や私的整理など、債務整理の選択肢を整理できる点が挙げられます。場合によっては、破産を回避できる可能性も探ることができますし、代表者個人の破産を防ぐ方法がある場合もあります。
複雑な倒産手続をスムーズに進められる
次に、様々な法律問題が潜む複雑な倒産手続を、弁護士に委ねてスムーズに進められることも挙げられます。倒産手続においては、法律に基づいた複雑な書類作成や裁判所とのやり取り、債権者や破産管財人との調整が必要です。これらの手続きを弁護士が専門知識と経験を活かして代行することで、経営者の負担を大幅に軽減し、スムーズに手続きを進めることができます。
経営者個人の連帯保証にも対応
また、経営者個人の連帯保証について、経営者保証ガイドラインも視野に入れながら対応してもらえることがメリットといえます。弁護士は、代表者個人の破産を防ぎながら、あなた自身が次の人生のステージを踏み出すことをアシストしてくれます。
まとめ
以上のとおり、飲食業の倒産・破産手続について解説しました。当事務所では、企業倒産・破産事件を多く扱っていますので、借金問題や資金繰りにお悩みの場合には、ぜひ、当事務所にご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014