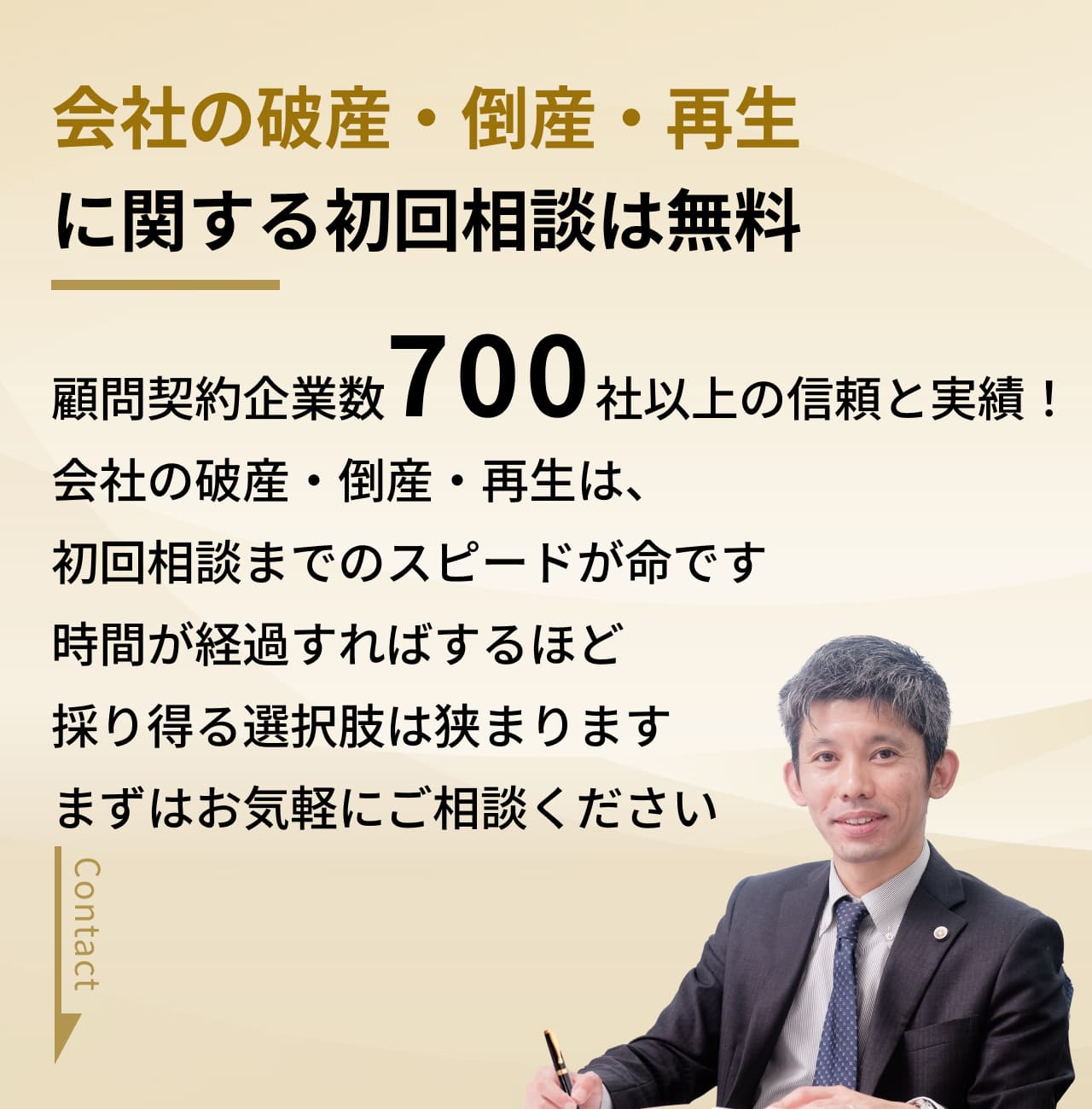昨今、物価高騰による買い控えや深刻な人手不足、ネット通販との競争激化により、小売業界はかつてない厳しい状況におかれています。「商品は売れないのに仕入れ値は上がる」「資金繰りが限界で、店を畳むしかない」と、苦渋の決断を迫られている経営者の方もいるのではないでしょうか。
特に小売業の場合、一般的な業種とは異なる悩みもつきものです。
- 店舗にある大量の在庫商品をどう処分すればいいかわからない
- テナントの解約や原状回復費用が工面できない
- 仕入れ先への支払いや連鎖倒産が心配
もし、お店の倒産や破産を検討しているなら、一刻も早く弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、小売業は在庫の不当な処分が法的トラブルを招きやすく、多数の取引先や顧客への対応など、専門的かつ迅速な判断が求められるからです。
適切な手順を踏むことで、混乱を最小限におさえられます。
本記事では、小売業の倒産・破産手続きの流れや特有の注意点について、弁護士が詳しく解説します。最後までお読みいただければ、複雑な問題が整理され、冷静に次の行動を選択できるようになるでしょう。
この記事でわかること
- 小売業が倒産する主な要因
- 在庫処分やテナント対応など特有の注意点
- 破産手続きの具体的な流れ
- 弁護士に依頼するメリット
【記事のまとめ】
小売業界は、物価高騰や消費低迷、ネット通販との競争激化などにより、経営環境が急速に悪化しています。小売業の破産手続きでは、店舗にある大量の在庫商品の適切な処分、テナントの原状回復や明け渡し、従業員の解雇など、迅速かつ専門的な対応が求められる課題が山積しています。
これらを自己判断で処理しようとすると、在庫の不当廉売とみなされたり、関係者とのトラブルを招いたりするリスクがあります。早期に弁護士へ依頼することで、複雑な手続きや債権者対応を一任でき、混乱を最小限に抑えて適切な整理が可能となります。円滑な解決のために、まずは弁護士法人グレイスへご相談ください。初回相談は無料です。
目次
小売業の倒産・破産が発生する要因とは?
2024年は各業界の倒産件数が激増した年となりました。スーパーやドラッグストアは赤字が続いて続々と閉店し、また、インターネット通販・ECサイト運営などの無店舗小売業の過当競争による倒産も相次いでいます。今小売業は、物価高騰や人手不足、賃上げに伴う人件費高騰など、未曾有の不況に悩まされているといえるかもしれません。
では、まず小売業の倒産・破産が発生する要因についてご説明します。
物価高騰
最初に挙げられるのが、物価高騰です。物価が上がることで消費傾向がしぼんでしまったことが挙げられます。物価があがったことで小売業者の販売する物品の価格はあがったのですが、これに追いつくほどには、家計収入(可処分所得)が増加していないのです。
人件費高騰
次に、人件費高騰の問題が挙げられます。人件費が急激に上がったことで、小売業者の利益が削られ、経営が圧迫されてしまいました。これが原因で赤字になってしまったり、借金をせざるを得なくなったりする業者が倒産に追いやられているといえます。
人手不足
また、人件費に関連することとして、人手不足の問題も挙げられます。近時は、タイミーなどの細切れの時間で就労するアルバイト的従業員が増加傾向にある一方で、特定の店舗・業者に定着する人手は減少しています。
この問題は、小売業者が黒字倒産する一因となっています。
競争の激化
特にインターネット通販等の無店舗小売業の分野では、様々な業者の参入が続き、競争が激化しています。このため、商品の価格競争が激化して価格が大きく減少する事態(価格破壊)に至ってしまい、小売業者の利益が大きく減じられる結果となっています。
無店舗小売業の分野では、廃業して市場から撤退する業者が多く出始めてしまっている状況といえます。
「ゼロゼロ融資」の返済負担
また、コロナウイルス感染症蔓延中に行われた「ゼロゼロ融資」の返済が始まったことも、小売業者の経営を大きく圧迫しています。ゼロゼロ融資が始まった際には、ゼロ金利であるがゆえに、「とりあえず借りてとりあえず設備投資する・当座の資金需要を賄う」といった対応が散見されました。
しかしながら、ゼロゼロ融資によって売上が増加するような結果になった事業主は多くはありません。このため、ゼロ金利であるにもかかわらず、その返済に窮する小売業者が多く出てしまっているのです。
無店舗小売業の倒産について(2024年過去最多)
特に上記のとおり、2024年は無店舗小売業の倒産件数が過去最大となりました。インターネット通販・ECサイト運営は、新規参入障壁が小さいために手軽にかつ小資本でも始めることができる反面、過当競争となることが避けられませんでした。
このため、零細・中小事業主は、ある程度の大規模事業主・企業が参画してしまうと、規模を有する事業主・企業との価格競争にはなかなか対抗することができなくないのです。
小売業の倒産・破産における注意点
次に、小売業者の倒産・破産における特有の注意点について見てみましょう。
在庫処理
まずは在庫処理の問題があります。
食材などの生鮮品は消費期限があるため、破産手続開始前に可能な限り使い切るか、適切な方法で処分する必要があります。また、アルコール類などの在庫も正確に把握し、破産管財人への引き継ぎ準備を進めることが重要です。不適切な処分は問題となる可能性があるため、弁護士と相談しながら進めるべきです。
従業員への対応
次に従業員への対応が必要となります。
解雇の時期、未払給与、解雇予告手当、退職金などの精算を法的に適切に行う必要があります。従業員の社会保険の各種切替手続や離職票の交付など、解雇に伴う事務処理にも留意が必要です。
未出荷の商品や注文への対応(無店舗小売業)
また、無店舗小売業の場合には、既に注文がなされている未出荷の商品や、次から次へと続く注文をどこで止めるかなどといった対応の検討が必要となります。倒産手続を進める上では、どこかの時点で事業を停止させる必要がありますから、注文を受けることをストップしなければならないタイミングを決めなければなりません。
サーバー・ECプラットフォームの維持(無店舗小売業)
もちろん、無店舗小売業の場合には、無店舗小売業に利用していたサーバーやECプラットフォームを維持するかどうかも検討することが必要でしょう。基本的にはこれらの利用契約も解除することとなりますが、場合によっては、破産管財人との間で協議をするべき場合もあります。
いずれにしても、弁護士による専門的助言を受けて方針決定するべきです。
小売業の倒産・破産手続の流れ
次に、小売業者の倒産・破産手続の流れを簡単にご紹介します。
在庫処分
破産申立て前に、食材などの在庫を売却してしまうケースが多いです。申立て前に処分できない場合は、できるだけ長く保存し、破産手続開始決定後に破産管財人が処分します。
また、倉庫で在庫品を管理している場合には、倉庫業者との間で、(商事)留置権や集合動産譲渡担保権などの担保権が設定されていることもありますので、個別に法的交渉が必要な場合もありますから、ご注意ください。
破産にかかる資金の準備
弁護士費用や裁判所に納める予納金(主に破産管財人の報酬など)が必要です。最低でも百万円単位の現預金が必要となるため、経営者の手元資金や事業の売上金などを適切に管理し、破産費用を捻出できるように準備します。
売掛金や現預金がある場合にはそこから破産費用を捻出できますが、場合によっては売掛金の回収や在庫品の販売が必要なこともあるでしょう。
弁護士へ相談・依頼
これらの対応について検討する上でも、弁護士への相談・依頼は必須です。会社の経営状態が悪化して改善が見込めない場合には、ある程度の資金力がある内に、まずは弁護士に相談し、法人破産や再建の方法について最適な提案を受けましょう。
会社の経営状況次第では、破産手続を行うまでの必要はないかもしれません。
破産手続
弁護士に依頼した上で破産申立ての準備を行ったら、裁判所に必要書類を提出し、破産手続開始の申立てを行います。裁判官と弁護士との間で行われる債務者審尋(会社代表者の出席が必要な場合もあります。)では、破産手続開始要件を満たしているかどうかの審査が行われます。
この要件を満たした場合には、裁判所は、法人に破産手続開始原因があると認めて破産手続開始決定を行い、同時に破産管財人を選任します。破産管財人は、会社財産の管理処分権を有し、これらを管理する役割を担います。
財産の換価・配当
破産管財人は会社の財産を処分・売却し、現金に換えて(換価)、債権者に配当します。この際には、税金や賃金が優先的に支払われることとなりますので、大半の企業では、一般的な債権者への配当は非常に僅少となります。
この換価・配当手続は、債権者集会において債権者にも報告がなされます。
手続終了
財産の換価・配当が完了すると、破産手続が終了し、法人格が完全に消滅することとなります。
小売業の企業が破産・倒産を弁護士に相談するメリット
このような小売業者の破産・倒産を弁護士に相談するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
債権者との対応を任せられる
まず、弁護士が債権者に対して受任通知を送付することで、債権者からの直接の督促や取立てが禁止されますので、経営者は対応の負担から解放されます。破産前の企業の経営者の最大のストレスである債権者からの取立てを回避できることは、最大のメリットといえるでしょう。
従業員・在庫・取引先への対応がスムーズに
また、弁護士が介入することで、解雇手続き、未払金の清算、在庫の適切な処分、仕入れ先との取引関係の整理など、複雑な対応を法的に適切かつスムーズに進めることができます。
複雑な倒産手続を任せられる
何よりも、破産手続は専門的な知識を要する複雑なプロセスです。弁護士に依頼することで、申立て準備から裁判所での手続、財産の換価・配当に必要な協力までの対応を任せることができ、経営者の負担を軽減できます。
破産後の生活再建
何よりも、法人が無くなったのちも、経営者の人生は続きます。債権者からの取立てが止まることで、精神的な負担が軽減され、破産後の生活再建に専念できる環境が整うことも、大きなメリットでしょう。
まとめ
以上のとおり、小売業者の破産・倒産手続についてご説明しました。当事務所では法人にフォーカスした上で倒産手続のご依頼を受けています。このため、法人の倒産処理には自信を持っています。
ぜひお悩みの際には、当事務所にご相談ください。
 0120-77-9014
0120-77-9014