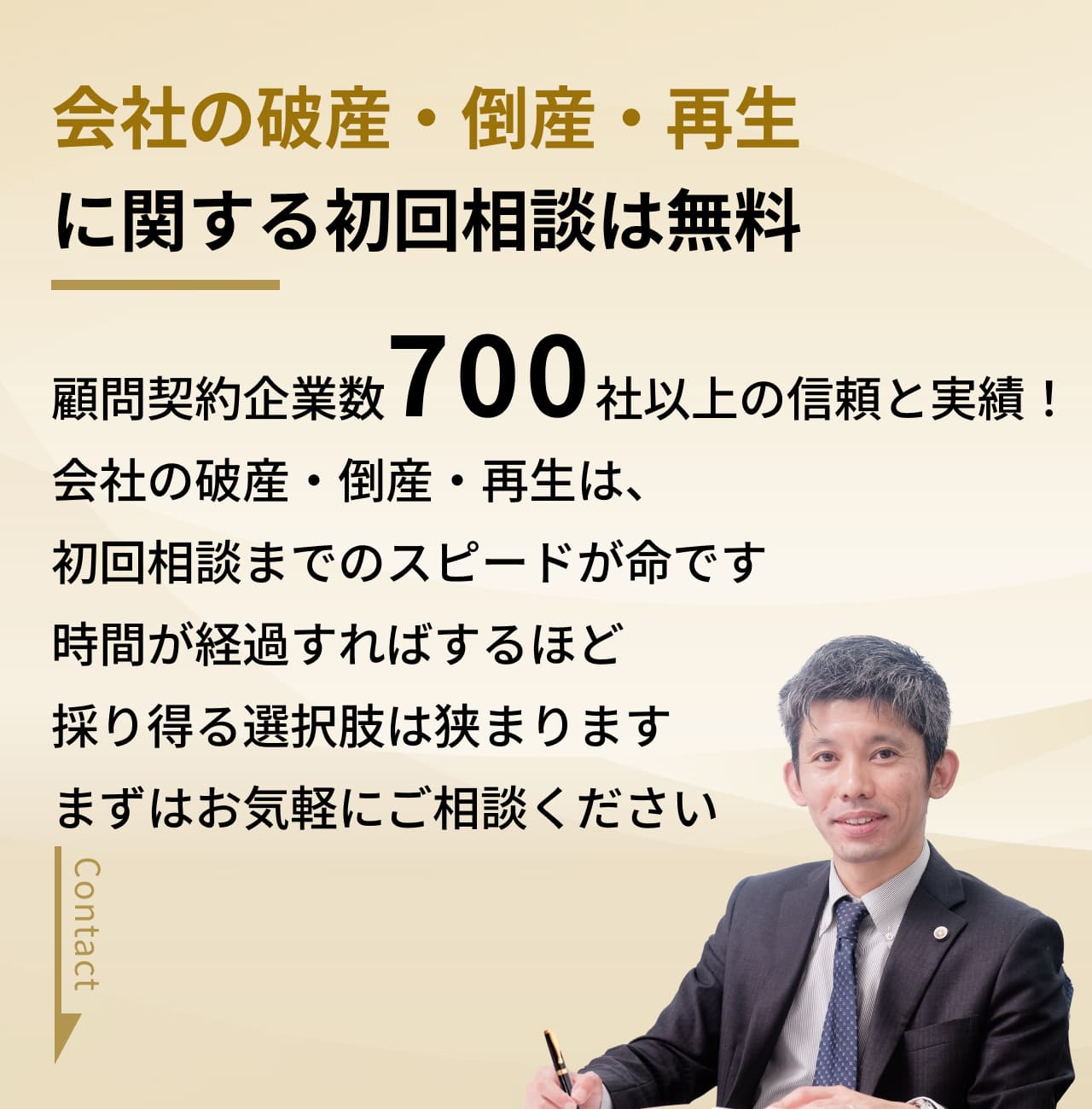昨今、人手不足の深刻化や光熱費の高騰、公定価格である報酬とコストのバランス崩壊により、福祉業界はかつてない厳しい状況におかれています。「利用者のために続けたいが、運営資金が底をついた」と、苦渋の決断を迫られている経営者の方もいるのではないでしょうか。
特に福祉施設の場合、一般的な事業の倒産とは異なる悩みもつきものです。
- 利用者の次の受入れ先がみつからない
- 指定権者(行政)への報告や手続きがわからない
- 職員の未払い賃金や再就職先が心配
もし、施設の倒産や破産を検討しているなら、一刻も早く弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、福祉事業は利用者の生活や命を預かる社会的責任があり、事業廃止には行政への届出や利用者調整など、高度な専門性が求められるからです。
適切な手順を踏むことで、利用者や地域への影響を最小限におさえられます。
本記事では、福祉施設の倒産・破産手続きの流れや特有の注意点について、弁護士が詳しく解説します。最後までお読みいただければ、複雑な問題が整理され、冷静に次の行動を選択できるようになるでしょう。
この記事でわかること
- 福祉施設が倒産する主な要因
- 利用者対応や行政手続など特有の注意点
- 破産手続きの具体的な流れ
- 弁護士に依頼するメリット
【記事のまとめ】
福祉業界では、深刻な人手不足や物価高騰により、経営環境が一段と厳しくなっています。福祉施設の破産手続きは、利用者の新たな受け入れ先確保や行政への届け出など、高い専門性と配慮が必要な作業です。
対応を誤れば、利用者の生活を脅かしたり、地域社会に大きな混乱を招いたりする恐れがあります。早期に弁護士へ依頼することで、複雑な手続きや債権者対応をすべて任せることが可能です。利用者保護を最優先にした円滑な整理を進めるために、まずは弁護士法人グレイスへご相談ください。初回相談は無料です。
福祉施設の倒産・破産が発生する要因とは?
皆さまは、2012年以降、高齢者用施設、障害者用のグループホームや保育園など、福祉施設の倒産・破産件数が増加傾向にあることをご存じでしょうか?
実は、2016年以降は毎年100件程度の福祉施設が倒産手続を取っています。少子高齢化が進む日本において、福祉施設の役割はますます重要になっています。しかしながら、その運営は多くの困難を伴い、残念ながら倒産や破産に追い込まれるケースも少なくありません。福祉施設の倒産は、利用者の方々の生活に直結するだけでなく、地域社会にも大きな影響を与えます。
福祉施設の経営が破綻する原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。主として、以下のような要因が挙げられます。
人手不足
福祉業界全体で、人手不足の問題が深刻化しています。求人を出しても応募がなく、必要な人員を確保できない施設が少なくありません。人手不足によって、サービス提供体制が脆弱になり、結果として経営悪化を招くのです。
人材不足
また、同様に人材不足も嘆かれています。有資格者を求人で確保することができないなどの問題が、人手不足の問題と相まって福祉施設の経営を圧迫しているのです。
更に、人手不足が解消されないことから既存職員への負担が増加し、人間関係の不満などが生じて経験者の離職が相次ぐケースも散見されます。これでは、福祉施設の維持をすることはできません。
介護報酬と人件費
また、どうしても介護報酬は国によって定められておりますから、施設の努力だけで売上を増やすことが難しいのが現状です。他方で、職員の人件費は物価高騰と共に上昇傾向にあります。特に昨今は、厚労省からの指示による処遇改善加算などにより、人件費が経営を圧迫する要因となることがあります。
競合の増加
これに加えて、介護保険制度の改定や、異業種からの参入などにより、福祉施設の数自体は増加傾向にあります。これによって過当競争が起き、利用者獲得競争が激化して定員割れを起こす施設が増え、経営が悪化する要因となるのです。福祉施設では、基本的には受入れ人数を増やすことでしか売上増加は見込めないため、過当競争の打撃は大きなものとなります。
福祉施設の倒産・破産における注意点
このような要因で倒産・破産に至りがちな福祉施設ですが、福祉施設ならではの倒産・破産における注意点があります。
利用者への事前の通知
最も重要なのが、利用者とその家族への丁寧かつ迅速な説明と通知です。福祉施設の閉業は利用者の生活に直接影響を与えるため、可能な限り早期に、誠意をもって情報提供を行う必要があります。この際には、他の施設への転居支援や、必要な情報提供を積極的に行い、利用者の混乱を最小限に抑える努力が求められます。
もちろん、事情によって利用者への事前通知ができない場合もあるでしょう。この際にどのような対応を取るべきかは、ぜひ弁護士とご相談ください。
従業員へのケア
また、倒産・破産によって福祉施設の従業員は生活の基盤を失うことになります。従業員を解雇せざるを得ない場合でも、可能な限り再就職支援を行うことが重要です。
ハローワークの利用案内や、地域の他の福祉施設の求人情報の提供、あるいは企業間の連携を通じて他施設の紹介を行うなどのサポートができると良いでしょう。まさに人手不足の業界ですので、同業態の他施設への紹介はスムーズに行いやすいです。
M&Aの検討
倒産・破産をすると、このように利用者や従業員に大きな影響を及ぼすこととなりますので、経営が悪化した場合でも、すぐに破産を選択するのではなく、M&A(企業の合併・買収)の可能性を検討することも重要です。特に最近は、福祉業界のM&Aが盛んです。
事業譲渡や株式譲渡により、施設の運営が継続され、利用者や従業員の雇用が維持される可能性がありますので、弁護士と連携し、早期に検討を進めることが望ましいでしょう。当事務所では、このような解決をした事例を複数経験していますので、お悩みの場合にはお問い合わせください。
福祉施設の倒産・破産手続の流れ
倒産・破産手続の流れもご紹介しておきます。
破産にかかる資金の準備
まず、破産手続を進めるには、弁護士費用、裁判所への予納金、従業員の未払賃金の一部など、ある程度の資金が必要となります。破産する上では、これらの資金を事前に準備しておく必要がありますので、本当に資金繰りが回らなくなる前に、弁護士にご相談ください。
弁護士へ依頼
弁護士に相談したのちに、実際にご依頼をいただくこととなります。破産手続は非常に複雑であり、専門的な知識が不可欠ですから、早期に弁護士に相談し、手続を依頼することが最も重要です。弁護士に依頼することで、煩雑な書類作成や裁判所とのやり取りなどを任せることができ、ストレスから解放されます。
また、弁護士に手続を任せることで、経営者自身が利用者や従業員のケアに時間を充てることが可能になりますので、まさに福祉施設の倒産・破産においては、弁護士への依頼が非常に重要であるといえるでしょう。
利用者と家族への対応
その後、依頼をされた弁護士と連携し、利用者とその家族に対し、破産手続きの状況や今後の見通しについて、丁寧に説明を行います。必要に応じて、他の施設への転居支援や、行政機関との連携も進めます。
もちろん、利用者やその家族への情報開示時期については、慎重な検討が要求されます。ぜひ、弁護士とご相談ください。
従業員への対応
従業員に対しては、解雇通知(解雇予告手当の支払い)、退職金の支払い、未払賃金の精算、離職票の発行など、お金に関する手続を正確かつ迅速に行う必要があります。
特に未払賃金に関しては、従業員に、破産手続開始決定後に未払賃金立替払制度を利用することについて説明をしておくべきといえます。この制度を利用すると、未払賃金の8割程度を国が代わりに支払ってくれる場合があります。
資産処分
破産手続開始決定後には、破産管財人(裁判所が、財産調査及び財産の換価のために選任する弁護士)主導のもと、福祉施設の資産を現金化していく作業が行われます。この際には、施設の所有する土地、建物、設備、車両などの資産を売却し、債権者への配当に充てることとなります。
この際には、各資産が、福祉施設特有の建築・間取りであったり、福祉施設特有の設備・車両であったりするため、まずは同業他社への売却を検討することとなります。
福祉施設の破産・倒産を弁護士に相談するメリット
このような福祉施設の破産・倒産を弁護士に相談するメリットは、主として以下のようなものとなります。
面倒な手続きを任せられる
破産手続では、法律に基づいて要求される複雑な書類作成や裁判所とのやり取りが多数発生します。これらの専門的な手続を、法律の専門家である弁護士に一任することで、経営者としては精神的な負担を軽減し、本来注力すべき利用者や従業員への対応に集中できます。
利用者家族、従業員への対応に時間を充てられる
また、弁護士が法的な手続をあなたの代わりに行う間、経営者は利用者とその家族への説明、転居支援、従業員の再就職支援など、倫理的に重要な対応に十分な時間を割くことができます。これは、福祉施設が担う地域的・社会的責任を果たす上でも極めて重要なメリットといえます。
経営者の個人の不安も解消できる
福祉施設の倒産は、会社の債務を保証する経営者個人の生活や将来にも大きな影響を与えます。また、債権者からの連絡が止まらない場合には、多大なストレスを抱えることともなります。
弁護士は、破産手続後の経営者個人の債務整理や生活再建についてもアドバイスを提供し、精神的な不安を解消する手助けをすることもできます。
まとめ
以上のとおり、福祉施設の倒産・破産手続の流れと注意点について解説いたしました。福祉施設は、ある種公的な役割をも担う場所ですので、倒産処理をする場合には、利用者・家族、従業員、地域といった様々な部分に配慮する必要があります。
当事務所では、法人破産の案件を多く扱っております。借金問題にお悩みの場合には、資金繰りが完全にショートする前に、早期に当事務所にご相談ください。あなたからのご相談をお待ちしております。
 0120-77-9014
0120-77-9014